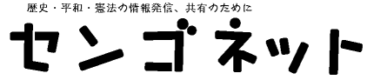改憲基準の考察―改憲の限界を確認する
[岸田改憲]来襲・3
====================

第26回参議院議員選挙(2022年6月22日公示・7月10日投開票)は、改憲の「関ケ原」となり、岸田改憲陣営は、非改選議員との合計で、改憲の発議に不可欠の参議院の総議員(248人)の三分の二(166人)以上の議席(179人)を確保した。
その内訳は、自由民主党の議員、119人、公明党の議員、27人、日本維新の会の議員、21名、国民民主党の議員10名、無所属の議員、2名(上田清司氏{埼玉県選挙区}、平山佐知子氏{静岡県選挙区})である。
衆議院では、岸田改憲陣営は、衆議院の総議員(465人)の三分の二(310人)以上の議席(345人)を確保している。
その内訳は、自由民主党の議員、261名、公明党の議員、32名、日本維新の会の議員、41名、国民民主党の議員、11名である。
なぜ、第26回参議院議員選挙を改憲の「関ヶ原」(運命をかけて戦う、この一番という戦いの意味に用いられる言葉)と位置づけるかと言えば、本シリーズ第2回で述べたように、アメリカのジョゼフ・バイデン大統領政権は、2027年に中国が台湾に侵攻するとの仮説を立てて、2021年3月から、「米中戦争」を始める準備を遂行しており、日本国も、「21世紀日米同盟」体制のもとで、「2027年米中戦争」に参戦できるよう、その参戦準備を2026年までに完了しておかなければならない。そのためには、自衛隊を「国軍」にするための自衛隊を日本国憲法に明記する改憲、「戦時体制」や「戦時国民動員体制」を作るための「緊急事態条項」を日本国憲法に導入する改憲などが不可欠であり、そして、その改憲を果たして、それの施行を可能とするためには、第26回参議院議員選挙を出発点としなければ、改憲破綻に陥ることになる可能性が極めて高いからである。
改憲の「関ケ原」に勝利した岸田改憲陣営は、改憲案を作りそれを国民に承認させる攻勢をかけてくる。
この攻勢を排撃するには、反改憲陣営は、岸田改憲陣営の改憲案を作り、それを国民に承認させようとする改憲運動とその改憲案を批判できる憲法理論を持たなければならないし、更に、岸田改憲陣営の改憲運動を立往生させる運動理論とその運動体制を持たなければならない。
そこで、この課題に取り組む。
1.岸田改憲陣営の改憲運動と改憲案を批判するための憲法理論
改憲を実現する方法には、立憲主義的改憲方法と非立憲主義的改憲方法がある。立憲主義とは、基本的人権が保障され権力分立制が定められた憲法に基づいて、権力の行使が行われることを言う。端的には、憲法に基づく権力行使のことを言う。
立憲主義的改憲方法とは、現存有効の憲法が定める改憲手続きとそこから導き出される改憲基準を踏まえて行われる合憲的改憲方法のことである。非立憲主義的改憲方法とは、現存有効の憲法が定める改憲手続とそこから導き出される改憲基準を無視し、精神的暴力(暴論)と物理的暴力(暴動)を用いて行われるクーデター的改憲方法のことである。別の言葉で表現すれば、「改憲クーデター」となる。
「改憲クーデター」について、クーデター(coup d’État)とは、フランス語で、同一勢力内での武力を用いての政権の打倒活動・略奪活動を意味する言葉であるが、それを利用して、当該憲法の改憲手続とそこから導き出される改憲基準を破り、精神的暴力と物理的暴力を用いて、憲法の全部又は一部を停止したり、改変したり、廃棄したりする行為を、「憲法クーデター」と定義する。
日本国憲法における改憲手続とそこから導き出される改憲基準は、次のようになる。
先ず、「改憲手続」については、「第九六条」において、「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする」(第一項)、「憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する」(第二項)と定められている。加えて、「第九九条」において、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と定められている。
日本国憲法の「改憲手続」に「第九九条」の「公務員の憲法尊重擁護義務」を含めるのは、日本国憲法の理想とする改憲を破壊する改憲暴走(非立憲主義的改憲)を阻止するためである。
次に「第九六条」と「第九九条」を合わせて形成される日本国憲法の改憲手続から導き出される日本国憲法における「改憲基準」は、次の通りである。
第一に、日本国憲法における憲法改正権(改憲案起草権・改憲案国会提出権・改憲発議権)は、国会(国会議員――衆議院議員と参議院議員)と国民のみが保有している。内閣には、憲法改正権は認められていない。従って、内閣を構成する内閣総理大臣とその他の国務大臣にも、憲法改正権はない。そのことは、内閣の「職権」を明記している日本国憲法「第七三条」に改憲の発議権が明記されていないことからも明らかとなる。従って、内閣総理大臣とその他の国務大臣が改憲活動を行ったら、「第九六条」の改憲手続違反だけでなく、「第九九条」の「国務大臣の憲法尊重擁護義務」違反にもなる。
第二に、日本国憲法が採用している改憲の方法は、「第九六条」が定める方法のみである。それは、(1)改めようとする条文や条文内の言葉を明記した改憲案を、(2)衆議院と参議院で、それぞれの総議員(法定数の総議員)の三分の二以上(三分の二を含む)の賛成で決定し(発議し)、(3)その改憲案を国民投票に付して、国民の承認を得る(国民の承認は、過半数の賛成で成立する)、という国民投票付「明文改憲」の方法のみである。
条文や条文内の言葉をそのままにして、解釈で条文や条文内の言葉の意味を改める改憲である「解釈改憲」は、許されてない。
公職選挙法によれば、衆議院議員の法定総議員数は、465人であり、参議院議員の法定総議員数は248人である(第四条)。その三分の二は、衆議院の場合、310人となり、参議院の場合、166人となる。
日本国憲法に基づく改憲の手順は、次の通りである。
一番目に、一つの改憲案を衆議院の総議員(465名)の三分の二以上(三分の二(310名)を含む)の賛成及び参議院の総議員(248名)の三分の二以上(三分の二(166名)を含む)の賛成で可決しなければならない(憲法第九六条第一項)。この可決で、国民に改憲が発議されたとされる(国会法第六八条の五・第一項)。国会議員が、改憲案を可決=発議するためには、衆議院においては、議員百人以上、参議院においては、議員50人以上の賛成が必要となる(国会法第六八条の二)。衆議院と参議院の憲法審査会も、改憲案を審査するだけでなく、改憲案を国会に提出できる(国会法第一〇二条の六・第一〇二条の七)。
国民に発議できる改憲案の内容については、国会議員は、「憲法尊重擁護義務」(憲法九九条)を有しているので、日本国憲法の全体及び前文と各条項の内容を悪くする改憲案を発議することはできない。それをすることは、国会議員の憲法尊重擁護義務に違反することになるからである。従って、日本国憲法のもとでの改憲案の発議は、日本国憲法の全体及び前文と各条項を良くする改憲案の発議(本当の意味の憲法の改正)しかできないことになる。日本国憲法は、〝護憲の団塊〟である。
二番目に、発議された改憲案を国民投票にかける期日は、改憲案発議後、速やかに、国会が議決する(国会法第六八条の六)。
国民投票は、国会が改憲案を発議した日から起草して六十日以後百八十日以内において、国会の議決した期日に行われる(日本国憲法の改正手続きに関する法律。以下、改憲手続法とする。第二条第一項)。
日本国民で年齢満18年以上の者が、国民投票の投票権を有する(改憲手続法第三条)。普通教育を終えた人は、社会人として働くことができるから、満15歳以上の者に国民投票の投票権を与えてもいいのではないか。
国民投票は、それのみで単独で行うことができるし、国会の定める衆議院議員総選挙の時か参議院議員通常選挙の時かに抱き合わせで行うことができる(憲法第九六条第一項)。
三番目に、国民投票において、「過半数の賛成」があったとき、改憲案が承認されたとなり、改憲が実現する(憲法第九六条第一項)。
問題となるのは、「過半数の賛成」について、日本国憲法が何の過半数(二分の一プラス一)なのかを示していないことである。
何の過半数かは、改憲の成立にとって、とても重要であるので、国民投票を実施するための法律を制定する際に、慎重に決定されなければならないが、理論的には、有権者総数の過半数か、投票者総数の過半数か、有効投票総数の過半数かの何れかとなる。
改憲の重要性から、多くの国民の投票による改憲が望ましいこと、日本国憲法が改憲の要件として、衆議院と参議院でのその総議員の三分の二以上の賛成による改憲の発議に加えて国民投票の過半数による賛成という厳しい基準を設置して、安易な改憲を戒めていることなども踏まえれば、日本国憲法のもとでは、投票者総数の過半数が、最低基準となる。
なお、法律の制定手続より厳しい改憲手続を定めている憲法のことを硬性憲法と呼び、法律の制定手続と同じ水準の改憲手続を定めている憲法のことを軟性憲法と呼ぶ。日本国憲法は、法律の制定手続(原則、衆議院と参議院での出席議員{総議員の三分の一以上であること、憲法五六条第一項}の過半数の賛成で法律は制定される。憲法第五六条第二項・五九条)より厳しい改憲手続を定めているので、硬性憲法である。権力者による改憲の弄を阻止しようとする意図が示されている。
「改憲手続法」(2007年5月14日制定)は有効投票総数の過半数を採用している(第一二六条)。この過半数は、棄権率が高く(投票率が低く)、無効票が多い場合、極少数の賛成で改憲が実現する。与党勢力が改憲派の場合、その改憲陣営はそのような状況を作ることができるので、有効投票総数の過半数は、与党派改憲陣営の為の不平等な手続となり、硬性憲法の意義を無くしてしまう結果をもたらすことになる。
与党派改憲陣営にも、反改憲陣営にも平等な改憲手続の最低基準は、投票者総数の過半数となるので、もし、有効投票総数の過半数を採用する場合は、必ず、一定の投票率がないと国民投票の不成立を宣言できる「最低投票率」制度を設置しなければならない。しかし、「改憲手続法」は、「最低投票率」制度を設置していない。それだけでなく、「最低投票率」制度の設置は、硬性憲法から導き出される絶対的改憲要件であるので、「改憲手続法」の中に絶対に設置されなければならない。
これまで、日本国憲法の認める改憲を実現するための改憲手続とそこから導き出される改憲基準(改憲の方向)を検討してきたが、日本国憲法は、その方向とは逆の、その改憲手続を用いても改憲を許さないという「聖域」をも、定めている。
改憲は、憲法の制定(「制憲」)後に可能となる行為であるので、改憲と制憲は、同一の行為ではない。
制憲には限界はないが、改憲には限界が存在する。
改憲の限界とは、第一に、改憲によって、制定された憲法典(憲法と呼ぶ文書)と似て非なる憲法典に変えてしまうことや制定された憲法典と全く別の憲法典に変えてしまうことは、制憲になるから、そのことはできないということである。
第二に、改憲によって、憲法を制定した権力――憲法制定権力(主権)を消滅させること(例えば、国民主権を君主主権に変えること)は、制憲となるから、そのことはできないということである。
第三に、憲法典に設置された改憲手続の「硬性主義」(法律の制定手続より厳しい改憲手続であること)は、憲法典の安定化を図ると同時に時代の変化や政治の変化に憲法典を対応させ、存続させるための「命綱」であるので、改憲によって、その「硬性主義」を「軟性主義」(法律の制定手続と同水準の改憲手続であること)に改めることは、制憲となるから、そのことはできないということである。
日本国憲法は、改憲の限界について、次のように明示している。
(1)「日本国民は」、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」。「われらは、これ(人類普遍の原理としての国民主権のこと――引用者)に反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」(前文)。
(2)「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」(第九条第一項)。
(3)「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」(第一一条)。
以上の規定を手掛りにして、日本国憲法における改憲の限界をまとめれば、「第九六条」の改憲手続を用いても、(1)古典的な人類普遍の原理である「国民主権」(日本国憲法の憲法制定権力)を改めて、天皇主権や国家主権にすることはできない、また、(2)古典的な人類普遍の原理である「基本的人権享有」を改めて、基本的人権を保障しないとすることや国家の必要によって制限・剥奪される基本的人権にすることはできない、更に、(3)20世紀に人類普遍の原理となった「非戦・平和主義」を改めて、「第九条」に反する武装・平和主義や武装・戦争主義を採用することはできない、というのが日本国憲法の態度である。
この結果から(1)と(2)と(3)に挙げられた3つの原理は、日本国憲法の固有性を表すその基本原理とされるものであるので、日本国憲法は自己の基本原理を改めて、自己が、自己と似て非なるものになること、あるいは、別のものになることを拒否していると考えられる。
そうであるならば、日本国憲法の基本原理は、先の3つの原理のみではなく、地方自治(第八章)と日本国憲法の「命綱」となる改憲手続の「硬性主義」(第九六条)が含まれるから、次のことを加えることができる。
日本国憲法は「第九六条」の改憲手続を用いても、(4)「地方自治」の原理を改めて、地方自治を設置しないとすることや国家の必要によって制限・剥奪される地方自治にすることも拒否している、(5)「改憲硬性主義」の原理を改めて、国民投票を実施しないとすることや、国会の発議を否定して内閣の発議のみにすることや、国会の発議を各議院の総議員又は出席議員の過半数とすること及び国会の発議に衆議院の優越を認めるようにすること(参議院が改憲発議を否決しても、衆議院の改憲発議があれば、それを国会の改憲発議とすること)などは、法律の制定手続と同水準の改憲手続にすること(「改憲軟性主義」にすること)になり、権力者(国会議員と国務大臣)が憲法を劣悪にすること、改憲を国民統治の道具にすることを許すことになるので、そのことも拒否している。
参考として、外国では、例えば、「イタリア共和国憲法」(1947年12月27日制定)は「共和政体は、憲法改正の対象とすることができない」(第一三九条)と定めている。(続く)