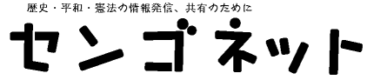ポストコロニアル文学の白眉、いまよみがえる小林勝

原佑介『禁じられた郷愁 小林勝の戦後文学と朝鮮』(新幹社 2019年)
『禁じられた郷愁 小林勝の戦後文学と朝鮮』(原佑介著/新幹社)を読む
作家・小林勝(1927年〜1971年)は1950年台後半から1970年代初頭にかけて「フォード・一九二七年」(1956年)、「断層地帯」(1958年)、「架橋」(1960年)、「蹄の割れたもの」(1969年)、「万歳・明治五十二年」(1969年)など数多くの小説や評論を発表し1971年に43歳の若さで没した。
作家デビュー間もない1955年に新日本文学会入会。多くの作品を『新日本文学』誌に発表した小林勝だが、本書の著者の原佑介は『新日本文学』の最後の編集長を務めた鎌田慧の次のような指摘を紹介している。「戦後文学は、戦争についてはそれなりに豊かな作品群を持つことができたが、小林勝のように、被植民地人民の敵意を描くことはなかった。」「戦争について書かれた作品はけっして少ないものではない。戦争に駆りたてられた兵士や空襲や疎開の悲惨な記録はそれなりにあるが、小林勝のように、植民者が被植民者の目を意識した作品はさほどない」
小林勝は植民地時代の朝鮮半島や朝鮮戦争下の敗戦間もない日本を舞台にした小説を多く残し、日帝の朝鮮半島侵略、植民地支配、今に至る朝鮮人差別と正面から向き合った、数少ない作家として貴重かつ、きわめて重要な作家だ。本書は小林勝の生い立ちから死までの全貌を明らかにし代表作をたどりながら、森崎和江、後藤明生ら植民者二世の作家たちを論じつつ、新日本文学の仲間たちの証言も交えながら小林文学の魅力を私たちの眼の前にあますことなく描き出している。
小林勝は植民地時代の朝鮮、慶尚南道(キョンサンナムド)晋州(チンジュ)で生まれ、幼少年期を慶尚北道(キョンサンホクド)の安東(アンドン)で過ごす。父親は植民地朝鮮の農林学校の教員だった。1944年16歳で内地にわたり埼玉県の陸軍予科士官学校に入学、17歳で終戦を迎える。小林の小説の舞台の多くは幼少年期を過ごした植民地下の地方都市だ。小林自身がモデルと思われる幼年期や思春期の少年が登場するが、植民地の朝鮮人と支配する側の植民者には巨大な「深淵」が横たわり、それは子供であっても変わらない。
原佑介が小林勝の最高傑作のひとつとしてとりあげている「万歳・明治五十二年」は1919年に朝鮮全土で起こった三一独立運動をリアルに描いた作品だ。自由な生きかたを求めて朝鮮に渡ってきた青年が田舎町に流れ着き、新聞記事を読んでいて京城や主要都市で独立運動の大デモが起きたことを知る。
やがて京城よりも数日遅れで田舎町にも独立運動が波及し、「マンセー、マンセー」のコールと共に太極旗を持ったデモ隊が大通りを埋め尽くす。青年は成り行きで日本人の自警団に加わり警察署に駆けつける。自警団の面々は「朝鮮人が近づいたらぶっ殺してしまえ」「かまうことはない、刀でたたき斬ってしまえ」と興奮状態に陥る。憲兵隊の銃声も聞こえデモ隊に犠牲者が出ると群衆は抗議の投石も始める。警察署周辺は大混乱となり、青年は混乱の中で自分でも気がつかないうちに銃を発射して朝鮮人を殺してしまう。青年は猛烈な罪悪感に襲われ絶句する。事件後、デモは鎮圧されたが報復を恐れ青年は銃を手放せなくなる。朝鮮人の怒りの冷たい視線が刺すように感じられ、小説のラストでは低いがはっきりとした日本語で「ヒトゴロシ!」という言葉を浴びせられる。手を朝鮮人の血で染めた青年の目の前に姿を現したのは、植民者—植民地暴力の行使者たる植民地主義者にとって「一切の理解を拒絶した、正体不明の、薄気味悪い外国人」だった。
「小林勝が凝視したのは、帝国の植民地支配によって植民者と被植民者のあいだに生じた巨大な「深淵」であった。なぜ朝鮮人と日本人のあいだには「拒否と被拒否という対極の関係」が今なお横たわっているのか。(略)朝鮮人の存在、日本人に向けられるそのまなざしを意識するものなどほとんどいない戦後日本社会で、小林勝は真剣にそのことを考えつづけた。」原は小林勝の文学の核心をこのように私たちに提示する。
「万歳・明治五十二年」が書かれたのは1969年だ。その前年の1968年は明治100周年として日清戦争、日露戦争に勝利した「光栄ある明治」がアピールされた年だった。明治は45年までなので明治五十二年は架空の年だ。原は小林勝がこの小説のタイトルをなぜ「明治五十二年」としたことの意味を投げかける。明治五十二年は大正八年で三一独立運動の年だ。「「明治百年」にかれ(小林勝)が対置させた「明治五十二年」––1919年とは、日本国民がいだくかがやかしい自国の来歴のイメージに含まれる歴史の暗部を象徴する年であった。」と原は指摘する。1927年生まれの小林は三一運動を直接体験したわけではない。だが実話をもとにしたらしく地方都市の独立運動は実際にこうだったのだろうな、と実感できるリアルさで小林の筆が冴え渡っている。
ポストコロニアリズムとは植民地主義のすさまじい暴力にさらされてきた人々の視点から西欧近代の歴史をとらえかえし、現代に及ぶその影響について批判的に考察する思想をいう(『ポストコロニアリズム』本橋哲也/岩波新書より)。朝鮮や台湾、満州を植民地とした日本もそこに加えても良いだろう。ポストコロニアル文学はポストコロニアリズムを体現する文学作品ということになる。
「万歳・明治五十二年」は植民者が植民地住民を殺してしまう小説だが、アルベール・カミュの「異邦人」もまたフランスの植民地アルジェリアに住むフランス人が植民地住民のアラブ人を殺してしまうという共通点がある。原は本書で「異邦人」をポストコロニアル文学として読解して目からウロコの思いがした。それだけでなく小林勝の文学は世界文学として位置付けられるような広がりを持つことにも気づかされた。
本書の最終章は小林勝の死の直前のエッセイ「「懐かしい」と言ってはならぬ」をめぐる考察が展開されている。在朝日本人の研究の先駆的な業績を残した歴史家、梶村秀樹をして「植民者の歴史的体験の再生の回路はこの言葉のなかにだけ含まれる」といわしめたと言及されているが、この言葉は植民地支配の歴史と向き合わねばならない現代を生きる私たちにも問いかけられているのではないだろうか。
小林勝は戦後、日本共産党に入党。朝鮮戦争下で日本共産党が武装闘争方針をとった時に武装闘争に加わり火炎瓶事件で逮捕され獄中生活も体験している。半生を綴った初期の自伝的長編小説「断層地帯」はこの時代のことが書かれている。日本共産党の武装闘争を伝える記録が少ない中、重要かつ興味深い作品といえよう。
本書が三一独立運動から100年目の今年3月、国を挙げての排外主義と歴史修正主義が跋扈する危機的状況にあるなかで出版された意味は大きい。今日の私たちが植民地支配の加害の歴史と向き合い、排外主義を克服していこうとするとき、小林勝のポストコロニアル文学はもっとも確かな水路となるものだ。本書は小林勝を読むための最良の水先案内人となるに違いない。(丸田潔)

小林勝(白川書院刊 小林勝全集第2巻より)
【読書案内】
原佑介『禁じられた郷愁 小林勝の戦後文学と朝鮮』(新幹社、2019年)
『戦争と文学』全20巻のうち第1巻、第15巻、第17巻(集英社、2011年〜2013年)
『戦後短編小説再発見7 故郷と異郷の幻影』(講談社文芸文庫、2001年)
『小林勝作品集』全5巻(白川書院、1975年〜1976年)

雑誌「人民文学」。1950年、「新日本文学会」から離れた江馬修や藤森成吉らによって創刊された雑誌。日本各地で発行されたサークル誌の中心的存在であり、安部公房、野間宏らの文壇作家や、小林勝、春川鉄男ら労働者作家、さらに在日朝鮮人作家等が参画した戦後民主主義文学運動の拠点であった。(「人民文学復刻版 1950年~55年」不二出版リーフより)

劇団民芸「檻」ポスター(1960年)。原作者は小林勝で演出は宇野重吉。第6回の岸田戯曲賞を受賞した。(「新劇、輝きの`60年代」関西学院大学リボジトリより)