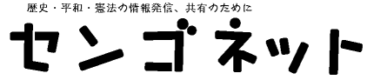マチズモの風見鶏:戦後日本の社会と石原慎太郎

石原慎太郎の死去を伝える「東京新聞」の記事
石原慎太郎元都知事(以下石原)が2022年2月1日に亡くなった、そもそもあまり文章を書く意欲が沸かない人物であり、結果として評価することになるのでは、とその気はなかったが、マスメディアが「賛美報道」を流しており、まさにファッショ的だったという意味で日本の難点を示していたことだ。評価としては、むしろ生前に石原と共に青嵐会で盟友だった故中川一郎元農水相の秘書も務めた政治家の鈴木宗男の発言が端的に表している。「政治家として個性のある方だが、結果として何かをしたということはなかった」(「週刊朝日」2016年10月28日号)
そして「アリの一言」というブログでもマスメディアの報道を批判している。そこでは識者として中島岳志東京工業大教授(週刊「金曜日」編集委員)の論稿(3日付沖縄タイムスなど=共同)を検討して<「石原への批判は、戦後日本を生きてきた私たちへの批判となって跳ね返ってくる」という結論>に嫌悪感を持ち、<「私たちへの批判となって跳ね返ってくる」という結論が、石原氏への批判を抑止>し、<石原氏への批判と有権者としての日本人の自省を抑止する論調は、歴史的汚点の隠ぺいに加担する>ものとして批判している。
https://blog.goo.ne.jp/satoru-kihara/s/%E7%9F%B3%E5%8E%9F
問題なのは<石原氏を「支持し続けた」人たち>とその背後のあるものに検討がないことだ、短い文章のなかでそれを表現するのは難儀かもしれないが、それがないと石原が支持された背景も見えないのでないか。
石原そのものは小説家から自民党の政治家となって、その後辞職し、東京都知事となった。政治家時代よりも都知事になってから発言がひどくなっている。結局のところ排外主義の右派ポピュリストというのが、石原の評価になるのだろうが、よりくだけて言えば「マチズモの風見鶏」で、「価値紊乱」の身軽さを持ちながら強者(米国や大勢)にのった戦後日本のある面を表した人物だったのだろう。
その意味で「激しい言動だが柔軟な思考のポピュリストを演じた」と報じた東京新聞もかなり大甘で、無理やりな感のある「演じた」という薄っぺらな評価でしかない。
ここでは斎藤貴男・吉田司『石原慎太郎よ、退場せよ!』(洋泉社 2009年)に依りながら、石原とそれが持て囃された背景をみていこう。
東京新聞では「毛沢東の論文「矛盾論」の方法論を高く評価していると語った」として「自分は狭隘(きょうあい)な人間ではない、とアピールする術すべを心得ていた」と評価するが、そもそも強いもの、勝馬につきたがる、「勝者の論理」を基準としているとの指摘がある(前掲書)。要は勝てればいわけで、無節操ということだ。
根本に右派の思想があるかといえば、「皇室にはあまり興味はないね。僕、国歌歌わないもん」と語り、「皇室は無責任極まるものだし、日本になんの役にも立たなかった」という信条だ。なのに都知事時代に国家斉唱を教員たちに強制し、従わないものを処分していた。あるのは自分で要するに自己中なのである。
https://biz-journal.jp/2014/03/post_4279.html
例えば日中平和友好条約(1978年)の決議時に青嵐会だった石原は決議に賛成した。本来ならば反対を貫き通すべきだが、思想・信条以前に「人として最も大切な部分が欠落」していると斎藤さんは断じている(前掲書75頁)。
さらに中国に北京五輪を開催する資格がない、と言っていたのが北京に招かれて開会式を評価して、その後は帰国してから、くだらないと語るのも(前掲書193頁)、基準がなく恥という概念もないのではないか。平気で掌の平返しができるのも融通無碍で無思想だからである。
石原の軌跡について、小説『太陽の季節』(1955年)は消費社会につながり、東京都知事になってからは戦後的な「価値紊乱」で新自由主義に乗っかっただけと端的な表現があるが(前掲書・斎藤)、敗戦後の日本は<天皇の上に米国が載った形で「国体」が再編された>(白井聡)形で、朝鮮戦争やベトナム戦争などを梃子として経済復興を成し遂げ、高度経済成長を経て経済大国となりバブル経済(1986年~91年)後は失速することになる。世界的な新自由主義グローバリズムにより日本は産業空洞化と格差拡大が進展した。
戦後日本のある時期に国民の総中流化という錯誤が生まれたが、早晩それは幻想であったことがあきらかとなる。女性の半分が非正規雇用となり労働者は不安定な状況に置かれているが、是正しようとする社会的意識は必ずしも高くない。
メディアが「勝ち組」「負け組」といった言葉で市場社会のなかでの競争を扇り、個々の人間が自己責任の意識を植えつけられていったせいだろう。思想的には新保守主義と一体となった新自由主義の意識操作により、保守的道徳観の復活、治安の強化、マイノリティの排除、排他的ナショナリズムなどを増長させた。まさに石原が放った発言と一致していったのだ。
結果として石原の遺したものは、碌でもないものだった。例えば石原都知事時代は海外旅行にはグランドキャニオンに妻と特別秘書が同行し、出張総額は2135万円だった(前掲書 129頁)。若手芸術育成としてトーキョーワンダーサイトを創るがそれに四男・延啓を重用、その友人夫妻の館長・副館長就任した。これは身びいきであり、「縁故主義(ネポティズム)」というものなのだが、安倍元首相のモリ・カケ問題がしっかり引き継いでいる。
また、何かと差別・排外意識を披瀝せずにはいられない言動(性格)についても、結果として優生思想によって人身を荒廃させることになった。世の風潮に乗ったかもしれないが社会的な責任の一端があるだろう。
重度障害者たちが治療を受けている病院を視察した石原は、会見にて「ああいう人ってのは、人格があるのかね」(99年)と発言し、それは間接的に相模原やまゆり園の障害者施設殺傷事件につながっていると思うが、これについても石原は「あれは僕、ある意味で分かるんですよ」(2016年)と優生思想を再確認・肯定するような話をしている。
https://biz-journal.jp/2017/03/post_18396_2.html
上記のようなヘイトクライムを誘発させただけでなく、公人でありながらさまざまなヘイトスピーチをたれ流した。これも当時は欧米であれば即刻辞任ものだと言われたのだが…。
陸上自衛隊の式典では「不法入国した多くの三国人、外国人が非常に凶悪な犯罪を繰り返している」(2000年)と発言し、蔑称としての「三国人」「シナ」の言葉を発している。これも在特会などあからさまに外国人(特に在日朝鮮人)を排撃する組織が現れる梅雨払いのような役割を果たした。漸くヘイトスピーチ解消法はできたが、ネットには差別表現が溢れ、ヘイト本が数多く出版され書店の棚を飾ることとなる。
極めつけは東京五輪招致を始めたことで(2005年)、直後に「日本をなめたらあかんぜよと(世界)に悟らせるために、東京のオリンピックを絶対に成功させたい」とまるでヤクザのセリフかのように発言している(前掲書 79頁)。さらに五輪開催のための候補都市の招致の応援演説でも、福岡の応援をした姜尚中に対して「怪しげな外国人が出てきてね。生意気だ、あいつは」と幼稚な排外意識を披露した(「朝日新聞」2006年8月31日)。
石原が壊したものは、単なるやさしさだったり、人と人のつながりだったり、寛容さ、他者・異物への尊重だが、それを社会のなかで大切なものだと再確認することが今後の運動の鍵ではないのか。
現状はまだ新自由主義によって導かれる世界が主流ゆえ、ネオリベ的思考に依り石原的発想する人は後を絶たないだろう。能力主義が強まっているし、残念ながらそれが転換する契機は見えないが石原が亡くなった今、改めて差別・排外の思想を許さないという意識を確認したい。
(本田一美)