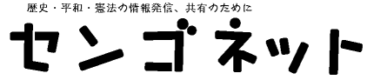軍国少女を育てた、藤田嗣治の「アッツ島玉砕」

書影
書評 ■ 『画家たちの戦争責任 藤田嗣治の「アッツ島玉砕」をとおして考える』 北村 小夜 (梨の木舎、1700円+税)
北村さんとは、今でも時々、「安倍靖国参拝違憲訴訟」や「即位・大嘗祭違憲訴訟」等で、お会いすることがある。そういえば、今年四月の、旧友・高橋寿臣の告別式や葬儀でも、お会いした。北村さんは今年で御年九三歳になるが、まだ六八歳ながら、心身共に、文字通り、ボロボロで、片足を棺桶に突っ込んだ状態の私などより、一見、よほど、お元気そうである。
その北村さんとの交流は、旧友・高橋寿臣を通しての、ことだった。もう大昔のことだが、高橋が北村さんのお話を聴く会というのを企画して、時々、北村さんのお宅に、何人かで押しかけて、お話を伺うというよりは、主に、ご飯を食べて、ああでもない、こうでもないと、(主に、高橋が)大声で語り合う集まりであったと、記憶している。
北村さんが、戦前、熱心な「軍国少女」であったこと、「女でも靖国に行くために」従軍看護婦として、満州に渡り、そこで敗戦を迎えたこと、戦後は、自らの戦争責任を問い続けるために、様々な運動に関わっておられることなどを、その集まりでの北村さんのお話で、私は知った。北村さんの行動や発言は、まったく、ぶれることがない。自らの戦争責任ということが、常に、その原点にあるので、日本の右傾化、戦争国家化への道を、北村さんは、決して、許さないのである。一切の詭弁やごまかしは、彼女には通らない。すごい人だし、失礼ながら、怖い人だと、私はその時、そう思った。
だから、恥ずかしい話だが、今でも、北村さんの前に出ると、私は足がすくむことがある。北村さんは、もちろん、何もおっしゃらないが、私のいい加減な生き方やごまかしを、見抜かれてしまっているような、そんな気がするからである。
北村さんの新刊は「画家たちの戦争責任」がテーマであるが、その前提には、「軍国少女」であった、自らの戦争責任があることは、もちろん、いうまでもない。彼女は、いう。「そんな軍国少女に私を育てたものは教育であり、歌であり、絵(戦争画)であった」「私の中にはその集大成として藤田嗣治の『アッツ島玉砕』がある。当時の人々に与えた影響を検証しておかねばならない」。
同書は、「戦争画のゆくえ 隠されたままの戦争責任」「そのころの子どもは、親より教師より熱心に戦争をした」「戦争画を一挙公開し、議論をすすめよう!」の、三つの各章と、関連資料からなる。
「戦争画のゆくえ 隠されたままの戦争責任」の中で、北村さんは、一九七〇年、菊畑茂久馬(一九三五年生まれの現代美術家)らが、アメリカからの「永久貸与」という形で、日本に戻され、国立近代美術館に保管されている153点の戦争画の公開を要求して、同館に突入する場に、ご自身も遭遇したと、記している。それに対し、国立近代美術館側の回答は、「いま公開すれば戦争賛美に解釈されかねない」「これらの絵画に対する国民の考えが定着してから発表する」「修復を必要とする作品が多く修復作業途上である」というものだったこと、それに対し、北村さんは、「作品を見て議論しなければ国民の考えは定まりようがない。それを『国民の考えが国に見合うようになったら公開する』というのだから、国家主義と言うほかはない」「修復と称して隠してはいけない。もし保存上どうしても必要なら公開しながら行うべきである」と、一刀両断している。
そして、その後の経緯について、次のように、書く。「それらは菊畑茂久馬らの要求にも応じることなく、恐らく著作権者の圧力、あるいは政府側の思惑によってのことであろうが、公開も移管もせず隠匿されてきた。一九七七年三月になって主な作品50点ほどが公開されるという報道があったので期待を持ったが、直前になって、戦争画の公開は東南アジア諸国の感情を刺激するという政府筋の思惑で中止になった。しかしこの公開中止はジャーナリズムの批判を浴び、近代美術館は七月から常設展に組み入れて、収蔵する戦争画のうち4点だけを公開するようになった」。
そして、最後の章で、北村さんは、「いま、わたしたちには様々な形で戦争の危機が迫っている。人々は政権にマインドコントロールされつつある。今やかつてのように美術がその一翼を担いかねない状況にある。国立近代美術館は一日も早く戦争画153点を一般公開して議論を進めなければならない。戦争画に唆され国のためと奮い立った私たちが生きているうちに」と、結論的に、主張している。
美術ジャーナリストで、画家の村田真さんが、自らが校長勤めるBankART schoolの講義録として出版した『いかに戦争は描かれたか』(BankART1929、1200円+税)の中で、国立近代美術館美術課長の大谷省吾さんは、「東京国立近代美術館の戦争記録画とその周辺」という文章で、次のように記している。
「一九七七年三月にとりあえず新収蔵作品展で、百五十三点のうち(修復を終えた)五十点くらい紹介しようとしたのですが、開催直前に中止になってしまう。なぜ、中止になったのか、いろいろ新聞雑誌で批判的に書かれ、東近美が悪者扱いされれるようになりました。隠すとはけしからんということですね」。そして、「どうして中止になったか、本当のところははっきりしていません」としつつ、おそらく、外部の有識者による委員会で、公開すべきという意見と、すべきでないという意見があって、後者が前者を上回ったのではないかと、推測している。大谷さんは、その当時、国立近代美術館に勤めておられたわけではなく、仮に、政府筋の圧力があったとしても、そんなものが、記録として、残されているハズもない。
しかし、同館が「決して戦争画を隠そうとしているわけではないことをアピールしようと、二〇〇〇年代はとにかくどんどん展示替えをして、今まで公開されたことのない作品を積極的に展示してきました。百五十三点の戦争記録画のうちすでに百四十数点は展示したというのが現状です」と、いうのである。
同館にしても、他の美術館にしても、確かに、その収蔵する膨大な美術品を、常に、すべて常設展示しているわけではなく、その大半は、特別な企画展でも開催されないと、観ることが出来ない作品であることは、事実である。そうした意味で、同館および大谷さんの主張には、一理あると、私的には、そう思う。
しかし、同時に、北村さんの主張もまた、しごくまっとうなもので、仮に、その大半をすでに公開したとしても、常設展に数点ずつ、ハッキリいって、紛れ込ませる形では、その全貌が、なかなか、把握しづらいこともまた、事実であろう。貴重な歴史資料でもある戦争画を、153点もまとめて収蔵する国の施設として、北村さんの主張に、何らかの形で応えていく必要は、当然、あると思う。
北村さんは、一九四三年九月二日、東京都美術館で開催されていた「国民総力決戦美術展」を訪れ、藤田嗣治の「アッツ島玉砕」を観たという。その時のことを、彼女は次のように書いている。「『アッツ島』の前に立った。藤田の会心の作であり、その後の死闘図の先駆けになったものである」「その凄まじさに思わず手を合わせる人もいた。そばにいた少年は、拳を握りしめていた。折り重なる死体、味方か敵か、生者か死者かの区別もつかない。断末魔の叫びが聞こえるような画面が、見る者の敵愾心を唆す。その場にいる人は皆、『仇を討たねば‥』と感じたに違いないと思った」。
ところが、その同じ絵を観て、評論家の加藤周一は、二〇〇六年五月二四日付『朝日新聞』に掲載された「藤田嗣治私見」の中で、「その画面には戦争賛美も、軍人の英雄化も、戦意昂揚の気配さえもない。――藤田は確かに軍部に協力して描いたが、戦争を描いたのではなく、戦場の極端な悲惨さをまさに迫真的に描き出したのである」と、北村さんとはまったく正反対の、見解を披瀝している。
それに対し、北村さんは、こう反論する。「私の愚かさは脇に置いても、『戦争賛美も、軍人の英雄化も、戦意昂揚の気配さえもない』と言われても、私を戦争に駆り立てたものに戦争画、中でも藤田の絵は強力であった。軍が委嘱した戦争画は後世に残すという役割もあっただろうが、当面は戦意昂揚が第1の目的だったはずである。敗戦後平和を目指すまなざしで鑑賞することは許されようが、その時見た青少年がどう受け取ったかで判断されなければならない」。
そして、北村さんは、「彼は自らの意志で戦争画家の道を選び、その地位を最大限に活用し、美術界にも大きな影響を及ぼした。私は、それを明らかにしないまま日本を去ってしまった(藤田の)責任を問いたい」と、主張する。
藤田は、一九四四年五月号の『美術』誌に、「戦争画制作の要点」という原稿を掲載し、その中で、「前線は勿論銃後一億国民が戦闘配置について、米英撃滅戦いよいよ愈々苛烈な決戦のこの秋に際し、美術界も亦奮然として未だ前例なき戦争展を開催し得た事は、実に大御稜威の御光と御賜と感謝する次第であり、更に我々はこの大戦争を記録画として後世に遺すべき使命と、国民総蹶起の戦争完遂の士気昂揚に、粉骨砕身の努力を以て御奉仕しなければならぬ」として、他の画家たちに戦争画制作の要点を指導までしているのである。その藤田に、戦争責任があることは、誰が見ても、明白であろう。
前述の『いかに戦争は描かれたか』の中で、藤田の研究家であるという林洋子さんは、「藤田嗣治――二つの世界大戦を経て」という原稿を寄せているが、「藤田は同時代の悲劇を採り込み、それを歴史画に転生できる画家」である云々と、書いている。そのことの是非はともかくとして、自らの戦争責任に関し、藤田が一言も語らず、この世を去ったことは、許されていいものではないと、そう思う。
くり返すが、北村さんは、藤田ら戦争画の制作者のみの戦争責任を、問うているわけではない。自らの戦争責任をも踏まえた、北村さんの、今の時代への危機意識は、私たちに広く、共有されなければならない。
是非とも、読んでいただきたい1冊である。
(土方美雄)

「アッツ島玉砕」藤田嗣治。東京国立近代美術館に所蔵(オンライン・ミュージアム MUSEYより)
https://www.musey.net/27269