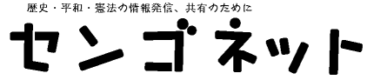もうひとつのオリンピック

人民オリンピックのポスター
https://wp.nyu.edu/specialcollections/2014/02/07/the-olympics-that-never-were-the-peoples-olympiad/
■五輪はみだし手帖
「喉元過ぎれば熱さを忘れる」ではないが、終わったことに人はさほど関心を払わない。東京五輪は開催されたが、それととともに「ちゃんと反対している人間がいるということを、それもちゃんと言葉で表現したい」(小笠原博毅『反東京オリンピック宣言』航思社 2016年)という思想ととりくみ、そして東京五輪とはなんだったのかを確認したい。
2021年の東京五輪が終了した。2020年の開催予定だったのがコロナウイルスの影響により、当時の安倍首相が自身の任期にこだわり1年延期するというスケジュールを設定した(森喜郎氏から2年延期を提案されたが言下に否定した)。
https://bunshun.jp/articles/-/47917
結果としてコロナは収まらず、これにより半数近くの日本国民が開催反対の意向を示し、2021年でも本当に開催できるのか疑問だった。しかし、「開催を中止する権利はIOCのみにある。開催都市側に、その規定はない」という。
https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-57125337
IOCとしては広告収入などが過去最高額に達するとも言われ、長期に放送権料などが確定していて収益確保に動いているという。
https://president.jp/articles/-/47225
もはやIOCは五輪の祭典を金儲けの道具として使い。それを覆い隠すために「アスリートたちによる、感動と平和の祭典」という謳い文句が唱えられる。実際に無観客での東京五輪が強行されて、それなりに感動し、楽しんだ人もいて、史上最多となる(58個のメダル)を取ったのだから、結果としては良かったと思う人もいるかもしれない。
しかし、東京五輪開催の事前活動を含めて、決定から実現に至るまで、そして直前の森会長辞任やIOCバッハ会長の「犠牲が必要」との開催強行発言などのあまたのゴタゴタを知ったうえで、以下の言葉を聞くと五輪大会は矛盾の集積としてあると得心しない人はいないだろう。
2020年東京大会は多くの矛盾ばかりを抱えたまま、むしろそれらの矛盾を原動力として開催に向かっているようにみえる。放射性物質の制御不可能性と「アンダーコントロール」発言に始まり、「復興」とグローバル・メガ・イヴェントの開催、還元されるわけがない一部の利権を生み出すために投入される公的資金。オリンピックの存在意義の確認作業を怠り、根本的な問題を棚上げしたまま盛り上げようとする「どうせやるなら派」。「感動」のもとに拒否できない空気のなかで促される「参加」。コンプライアンスの名のもとに自由を奪われるアスリート。利権に群がる巨大メディアの思惑に抗えない構造に組み込まれながらも標榜される「アスリート・ファースト」さらには、大会について意見を自由に表明したり疑義を差し挟む余地は文字通り消し去られ、社会をコントロールするための理由にされているオリンピック。
(小笠原博毅 山本敦久『やっぱりいらない東京オリンピック』岩波書店 2019年)
もはや五輪そのものが「巨大な権力となっていると同時に、別の権力に寄生され、それを増長させることのできる宿主となっている。宿主がそこにいる限り、寄生しようとする勢力は後をたたないだろう。しかしやがて宿主は食い尽くされ、死滅するだろう」(前掲書)とも指摘されている。まさに断末摩だが果たして寿命がつきて自然死するのか、それとも生まれ変わるのか不明だが、生まれ変わるにしても負の遺伝子を断ち切ることは可能なのだろうか。それを考えるためにも東京五輪を振り返ることに意味があるのだろう。
そのうえで「私からするなら、東京オリンピックに反対するなら瀬戸内国際芸術祭にも反対しなければならない。後者を条件付きであれ容認するなら、前者も同じ条件を付けて容認しなければならない」とアートイベントやスポーツや学術集会などは等価であるとする小泉義之の論考「競技場に闘技が入場するとき」(『反東京オリンピック宣言』航思社 2016年)は個別の具体的論考は掘り下げられていないので、説得的ではないが、原理的で重要な論点と思える。留意しつつあれこれ五輪大会と派生した問題について考えてゆこう。
東京五輪が国内統治の手段としてされ、政治利用に対して強く異を唱える意見はある。しかし統治以外でも以前から国威発揚の手段として利用されてきた。1936年のナチスのベルリン・オリンピックが典型だろう。それに対抗する反ファシズムとしての人民オリンピックがあったことを伝える『幻のオリンピック』(川成洋 筑摩書房 1992年)を紹介して、もうひとつの五輪のかたちを構想してみたい。
ベルリン・オリンピックが迫っていた当時のナチス政権は反ユダヤ政策をとっていて、それに対してボイコット運動が起こった。急先鋒はアメリカでユダヤ人が多く住むニューヨークで盛んだった。抗議運動が大きくなるなか、IOCは開催決定はワイマール共和国下のドイツだったことと内政不干渉を理由にして開催を撤回しないという結論を出した。36年6月にはパリでオリンピック精神の順守を目的とする国際会議が開かれ、すでに亡命していたハイリッヒ・マンはドイツのオリンピック組織委員会を批判する演説をおこなった。ドイツはIOC名誉会長のクーベルタン男爵をベルリンに招いて、1985年8月4日に「応援演説」をラジオで放送した。
1936年4月14日、スペイン・バルセロナに新設された競技場で共和国誕生5周年のイベントが開かれ、その一環としてナチスの獄舎につながれている反ナチスの闘志たちの釈放をスローガンとするスポーツ・フェスティバルが開かれ、その終了後に「もうひとつのオリンピック」を開催しようという案が提示された。「もうひとつのオリンピック」は「バルセロナ人民オリンピック」として7月19日から一週間と決まった。エントリーした選手は23ヵ国数千名に上った。性格としてナチス・ドイツに対抗する開催となったが、組織委員会としては偏向のないよう心がけたという。そして7月18日、開会式の前日に世界的に有名なパブロ・カザルスの指揮でオーケストラと合唱団ととも最終リハーサルをおこなっている最中に、反乱軍が市を攻撃していると告げられた。スペイン内戦の勃発である。
スペイン内戦により、バルセロナ人民オリンピックは中止となったが、異質の参加形態だった。従来は国別エントリーであったものが各競技種目の国際的組織が、その機関の決定として参加することも可能となった。ベルリンでの公式イベントと違い、女性が広く参加できた。開会式には、各国を追放されたユダヤ人や北アフリカの植民地出身の選手らが、国や国家を持たない民族の代表チームとともにスタジアムに入場することになっていた。国際卓球連盟、国際自転車連盟、国際アマチュア・ボクシング連盟なども全面協力の支援を表明した。労働者の体力向上やスポーツ愛好者の大会でもあるが国際的競技のレベルも志向した。
時代の刻印としてのまぼろしの「人民オリンピック」ではあるが、国のための競技というよりも、自治の理念と相互扶助と競争を求めたのである。もうひとつのオリンピックを夢想することは、困難なことかもしれないが、友好と平和の祭典を追求した試みを想起してみるべきではないのか。
(本田一美)

人民オリンピックのユニフォーム
https://wp.nyu.edu/specialcollections/2014/02/07/the-olympics-that-never-were-the-peoples-olympiad/