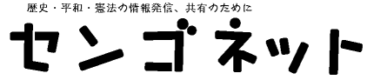最後の日本兵は台湾人だった!―戻らない日本兵

映画『ONODA 一万夜を越えて』より https://www.fashion-press.net/news/77824
当初は映画『ONODA 一万夜を越えて』(2021年10月公開)を観て映画評を書くつもりだった。事前情報で原作がべルナール・サンドロン、ジェラール・チェヌ共著の『ONODA 30年間密林で一人戦争』(1974年)だと知りった。これはフランス独自で出された本で、アジア太平洋戦争の認識などはどうなのか疑問だ。しかも劇映画ということでフィクションの占める部分が大きくなり、演出によって事実とは別な面を見せられるということになる。小野田元日本兵に関心はさほどないのだが、なぜ闘い続けたのかということには興味がある。この映画の監督は「彼自身の揺るぎない信念に僕は引き寄せらたんです」「想像では、小野田さんはあそこにいたかったのだ、と思いました。何かここにいたいと思わせる理由があったのではないか。日本にいる自分とは違う、何か違うものになれる場所だったから」と語っている。
「映画『ONODA』の原作者は仏高級ブランドのビジネスマンだった」
https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/jbpress/world/jbpress-67714?page=1
BANGER!!!
https://www.banger.jp/movie/61214/
結局のところ想像上の<闘う日本兵を描く>のみなのではないか、それならば、個人の想像というより、映画そのものを離れて、具体的にそのような日本兵のあり方を知ったほうがいいだろう。日本社会で注目された「最後の日本兵」よりも、派兵されて戻らなかった敗戦後日本兵の行方を考えてみたい。
まず小野田寛郎元日本兵がルバング島で発見された1974年に、インドネシアのモロタイ島でも中村輝夫という日本兵が発見された。中村輝夫は台湾・高砂族(アミ族)出身で後年は「李光輝」という中国名を名乗った。結局は元日本兵だが日本人ではない中村は台湾へ戻り、その後病没している。このように同時期に「最後の日本兵」(むしろ時期からいえば中村輝夫が最後のはずだ)として登場しならがら中村輝夫はさほど注目されず、日本社会にとっては小野田寛郎が圧倒的であった。
このように日本社会ではさほど注目を浴びない「最後の日本兵」の有り様を知るために『残留日本兵』林栄一(中公新書 2012年)を紹介する。
この本で注目するのは、1972年に発見された横井庄一もそうだが、上記の彼らは現地住民とは敵対的関係または無関係にあったとして、もう一方のアジア(ソ連を含む)に定着した残留日本兵に注意を喚起している。彼らが生きた「自文化でも異文化でもない境界領域を生きたという側面にもっと光を当てるべき」(前掲書)と主張する。
アジア・太平洋戦争で日本は約719万人が軍隊の動員されて、敗戦後の引揚者は318万5988人を数えた。そして残留日本兵の総数を一万人と仮定して、そのうち生い立ちや動機などの検証可能な100の事例をもとに議論を展開している。
例えば残留の理由は多様だ。「大日本帝国」の理想とされた大東亜共栄圏の理想を追って、その実現のためと残留した例(宮本滋夫)がある。また、北海道の農家出身の兵は日本に戻って農地をもらい自活する目途が立たず、その後はアジア主義を学び残留した兵(小野盛)もいる、ともに、インドネシア国軍に入っている。
あるいは自由を求めてタイ人と結婚し、引揚げ船から下船した人もいる。有名なマンガ家の水木しげるも派遣された島の原住民たちと仲良くなり、引揚げ時に現地除隊を上官に相談している。もし現地に留まっていたら「ゲゲゲの鬼太郎」は生まれなかったかもしれない。(『カランコロン漂泊記』水木しげる 小学館 2000年)
捕虜生活や人間関係が嫌になり、収容所から逃げ出した例もある。捕虜になった屈辱感に耐えられず、やりたいことをやってから死のうと脱走したり(山根良人)、朝鮮人や中国人に扮して逃げ出したり、戦犯になることを恐れてベトミンに入った例(石田松雄)もある。
総じて大日本帝国の滅亡やアジアの独立という大きな問題よりも、例えば戦前の現地滞在経験などで主体的に残留した場合もあれば、「家族、敗戦処理、捕虜生活んどの身近な問題に対処するうちに、個人的な性への渇望が生まれて残留していったように感じられる」(前掲書 78ページ)、つまり状況によって、生きることを選択していったということなのだろう。
いっぽう植民地出身者の場合は複雑だ。朝鮮や台湾からの日本兵は戦後の社会変動のなかで難しい立場に置かれた。敗戦によって敵対協力者として処罰されることを危惧したり、「祖国の裏切り者」となることを恐れて残留した例がある。この本には台湾の残留日本兵の例しか記載されていないが、朝鮮にも徴兵制(1944年)が敷かれて20万9千人が動員されて6千人以上が戦死した(『朝鮮人BC級戦犯の記録 』岩波現代文庫 2015年)という、内実についても朝鮮人兵士は「毎日ビンタを食わされるので脱走者が続出し殆ど捕まらなかった」(『わが懐かしき兵営生活』武田繁太郎―『草の根のファシズム』吉見義明 東京大学出版会 1987年 139ページより重引用)というから残留した兵士もいたに違いない(サハリンの在留朝鮮人は棄民というべきものだろう)。
日本軍兵士ゆえに敗戦後も日本軍の指揮系統に拘束されていたということも大きな問題だが、ここでは手に余る。
この本では「残留」という現象が、引揚げの対概念としてではなく、多様な戦い、生存の社会関係の束でもあったとして、当地の軍隊への加入や結婚して市民権を得るなど様々だったと紹介している。そして「残留日本兵」がマスコミで注目された意味について「横井や小野田が戦後の日本社会のある時期に大きく脚光を浴びたのは、戦後の日本人が彼らを鏡として過去の戦争を見ようとしていたからである」と解釈している。
残念ながら映画『ONODA』にまつわる報道や評価では、かつての軍国主義の亡霊というような見方はほとんどなく。むしろ「日本スゴイ」の類型として消費されているように見える。
要は日本人の自画像として、彼ら闘い続けた日本兵を称揚するという自家撞着なのだが、その闘い続けた場所はあくまでアジア人たちの場所であり、現地に留まる日本兵にとって、周りは敵であり、敵・味方の関係はは変わることはなかった。常に日本国家(大日本帝国)を後背させ、旧日本軍に拘束され続けたということをどう考えるのだろうか。そこには本人の自己意思はありえず、もっと言えば狂信的な存在としての人間しか見いだせないのではないだろうか。
なお、小野田少尉の手記を代筆した津田信によれば、彼は日本の敗戦を承知していたと語っている。その時期に矛盾があるにせよ、もはや潜伏すること自体が目的化していたのではないだろうか。(津田信『幻想の英雄-小野田少尉との三ヵ月』図書出版社 1977年/Kindle版)
日本人から見れば模範的日本人なのかもしれないが「アジアの人々にとっては、横井や小野田は、ジャングルに潜伏し続けたミステリアスで危険な存在でしかなかった」この応答を用意する必要があるだろう。そして多分にオリエンタリズムを相補的にすくい上げながら日本のありようが提示され続けてきた。
視点を変えよう。現地に残った日本兵についての見方を提示して「第二次世界大戦後、アメリカのヘゲモニーのもとでつくられた「日本とアジア」という地域秩序のなかで生きてきた私たちに、「アジアのなかの日本」という世界観のなかで、個人として自律的に生きる可能性を提示してくれている」(『残留日本兵』林栄一 中公新書 2012年)と書いている。それまでの共同体から離脱れ、別な選択をするということがあるのだ。
なにかと日本人は空気を読むことを強いられて、世間なかで調整・抑制しつつ生きていくことを求められてきた。戦争という例外状況のなか敗戦を迎えて、その「日本軍国主義」の鎖や錘が解き放されたときに ある日本兵は従来の国家やしがらみから解き放され、離脱できるし、生きるため、生存の自律的な活動を始めたのだと確認できる。
そのことが「生きるため」の指針を示しているような気がする。個人的にも水木しげるのように戦争中でありながら島の原住民と仲良くして、バナナや芋をもらってひとりだけ太っている(『カランコロン漂泊記』)、という話に憧れるのである。
(本田一美)