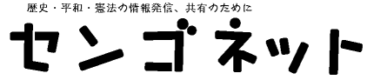第3回むさしの平和のための戦争展報告〜異なる声が重なる場について〜

むさしの平和のための戦争展バナー
「むさしの平和のための戦争展」は今回で3回目を数えた。1回目は2014年。「七三一部隊展」を中心に、医学・科学の加害責任について考えた。2回目の2015年は、日韓国交正常化から50年目ということで、「韓国・朝鮮人BC級戦犯展」を中心に、朝鮮半島と日本の関係を再検討した。いずれも、戦争、植民地支配における加害の側面に焦点を当ててきた。そして、日中戦争から80年目の今年は、南京事件(多様な呼称があるが、ここでは後述の番組での呼称に合わせこのように呼称する)を取り上げることにした。以下は、企画の詳細報告というよりも、開催までとその期間中に主催者の一人が見たこと、感じたことの記録ということになる。
南京事件をテーマの中心としたのには二つの契機があった。一つは、前回の企画における講演会の場(2016年は『日本鬼子』の上映会を実施)で、「南京事件は実際のところどうだったのか?」という主旨の質問があったこと。これを受けて南京事件についていつか取り組まなければならないと思っていた。
もう一つは、2015年に放映されたドキュメンタリー番組「南京事件 兵士たちの遺言」(日本テレビ系列「ドキュメント’15」)(以下、「兵士たちの遺言」)という番組に出会ったことだった。この番組は、昨今、「post-truth/ポスト真実」と名付けられた空気が世界中に蔓延している状況の中で、まさに事実に即した徹底した調査報道の手法にこだわって作られていた。この番組に出会ったことで、感情ばかりをフォローし事実を無視するような歴史認識が跋扈する現状に焦りを感じていた私たちは、やはり事実をきちんと伝える企画は重要なのだとの思いを改めて強くしたのであった。何らかの妨害はあるかもしれない。でも南京事件について取り組んでみようと決めたのであった。
南京事件を含めた中国戦線の実相を知るべく、非公式の写真班として日本兵の日常を記録した村瀬守保の写真展「写真が語る侵略戦争 村瀬守保写真展」を3月31日から4月3日までの4日間開催した。
村瀬は1937年7月の盧溝橋事件の折に召集され28歳で従軍生活を始めた。輜重兵として後方部隊に配置されたが、以前より写真が好きだった村瀬はカメラ2台を持ち兵士の日常を撮っていたところ、軍の非公式写真班として認められたのだという。2年半の従軍で撮った中国各地の写真は約3000枚が遺された。写真展の会場では、加害者の方々の証言ビデオも終日放映した。
また期間中、4月1日には、映画「陸軍登戸研究所」の上映と楠山忠之監督と学徒動員で風船爆弾製造に関わった小岩昌子さんとのトークショーが行われた。2日には、「南京百人斬り訴訟の顛末」と題し、同訴訟の弁護団を務められた穂積剛さんによる講演も行われた。来場者は、延べ850人を超えた。

展示会場で加害証言映像を見る人びと
毎回、展示会場、講演会場ではアンケートを実施している。その回収率もさることながら、1枚1枚に記されたそれぞれの思いの密度がとても濃い。いままで知らなかった事実を知ったこと、その上で考えさせられた思いなどが綴られる。その方の年齢や所属など環境により内容は様々だ。毎年、少数ではあるが、中国や韓国からの留学生の声もある。複雑な思いが長文の回答から伝わってくる。最後は、こうした企画への感謝であるとか、両国の人びとの友好を願う気持ちなどで締めくくられることが多い。こうした文面からは、こんどは逆にこちら側が、このように抑制された思いに応えるだけの努力を行っているだろうか?という葛藤をよびおこされる。率直にいって努力は足りていないと思う。
アンケートを通じて、企画者のわたしたちは、様々な方々との内面の交流の機会に恵まれる。本当は、他の来場者の方々へもこうした交流をシェアできたらよいのかもしれない。だが、センシティブな内容だけに、その場合には丁寧な時間をつくる必要があるだろう。いつか形にできたらと個人的には思っている。
中には、アンケートは書かれずに、でもこみ上げた思いを口にして帰られる方も少なくない。今回は、私自身、とても考えさせられてしまうことをお話しになって帰られた初老の男性の方がおられた。その方は、写真展と会場内で放映されていた加害の証言ビデオをご覧になられていた。熱心にご覧になられていたので、「ぜひアンケートを」とお伝えしたところ、それはご辞退された。だが、その後で、以下のようなことをお話しになられた。
写真展でも証言でも、「仕方がなかった」とおっしゃられている。でも、私の父母は、満蒙開拓の話が、村で出た時に、「それは、結局、中国の人たちから土地や仕事を奪うことになるのではないか」として参加を拒否した。すると、村八分のような状態になり、それは戦後にまで続いた。だから、「仕方がなかった」という言葉は、私には受け入れられないんです。
聴き漏らしたこともあったかもしれないし、私の記憶も曖昧なところもあるが、それでも、「仕方がなかった」ということで済ませてもらっては困るんだ、という男性の強い思いが私の胸にズシンと伝わったことだけは確かだ。
戦争への「加担」が当然視され、少しでも異議申し立てをすれば、非国民とののしられるような空気が戦時下に充満していたことは、戦後生まれの私でも伝え聞いて理解していた。だからこそ、そんな空気だったのだから仕方がなかったんだ、という言説を当たり前に受け入れていたのである。だが、中には、抵抗をされていた方もいた。非国民扱いという集団からの社会的排除を受けておられた方もいたのである。そうしたことも全く知らなかったわけではなかったが、そういう方々やそのご家族が、当時どのような思いでおられたのか、今どのように思われているのか、というところまでは想像できていなかった。だから、今回、率直な思いをお聞きした時、衝撃を受けた。まだまだ思いが至らないことがたくさんある。
事実が提示されたとき、特に、自身の所属する国家、社会の犯した加害の事実が目の前に提示されたとき、人は様々な形で衝撃を受ける。そして、それを消化することはたやすくない。その過程ではきっと各人が自身に引きつけ、そしてそれぞれに思いが生じることになる。逡巡が続くかもしれないし、そもそも引きつけることを拒否することもある。このような状況は今企画でも具に感じられた。その中で、今回気づきを得たことがある。それは、こうした企画というのは、事実の提示から始まり、そこから受け手それぞれに思いが生じ、それは発露される。そうした場となっているのではないかということだった。立場の異なる声や思いが提出される場。そのような意味で開かれた場として機能しているのではないかと。だとするならば、よりいっそう、投げかける事実に対しては誠実な提示のあり方が求められるだろうし、同時に投げかけた後のコミュニケーションにももっと注意を払う必要が出てくるだろう。
いま、異なる声や異なる立場がなかなか重なれない。重なるどころかぶつかる場さえ乏しい。排除や暴力の増幅が止まらない現状の中で、異なるもの同士が容認される場はわたしたちが抗える場となるのではないだろうか。そんなことを思った。
最後に、今回の企画にご来場くださったみなさま、ご協力くださったみなさまに心からお礼を申し上げたい。どうもありがとうございました。(五郎丸聖子)


村瀬守保の写真に見入る人