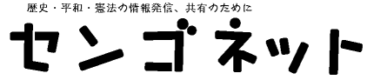人柱にされた「特攻」を考える
12月18日に中野区産業振興センターで『川端康成と「特攻」没後50年に思う』というタイトルで講演会が開かれた。講師は作家の多胡吉郎さん。主催はABC企画委員会。
集会のチラシに主旨があるので紹介しよう。「2020年は川端康成没後50年であった。日本の伝統美を象徴する作家として語られる川端だが、敗戦濃厚な1945年の4月から一か月、海軍報道班員として鹿児島鹿屋の特攻隊基地に滞在した事実はほとんど知られていない。この特異な戦争体験がどういうものであったか。そして戦後の川端文学にどう影響したのか。極限の生死をかけた「特攻」を切り口として、川端文学への新たな視点を探ると同時に、生命(いのち)の尊さを考える機会としたい。」とある。
多胡吉郎(たごきちろう)さんは、これまでの川端文学の研究のなかで、戦時中の特攻隊基地での体験が見過ごされていて、鹿児島県の鹿屋(かのや)での、特攻隊員とのふれあいや体験が作品に影響を与えていると語る。
その事例として小説では『生命の樹』(1946)と『紅いくたび』(1950~51)があり、随筆では『敗戦のころ』(1955)と『水郷』(1965)があるという。
多胡さんは、川端自身が特攻隊員たちが突撃までの日々を暮らす宿舎で寝食をともにし、米軍の空襲時にはともに防空壕に避難し、さらに遺書や遺品にも目を通したであろう。そのことが影響を受けないわけがない、と言う。鹿屋の特攻基地跡に赴き地下壕、それに特攻隊へ送る電信を受信する電信室を取材したことを語り、地下壕の暗闇のなかでそのモールス信号を聴いて川端康成も衝撃を受けたのではと追想した。
また、川端康成と出会ったであろう特攻隊員も特定し、それらの人となりがわかる資料や遺書も紹介した。川端の「特攻」についての小説には、女性の視点が顕著だという。
その後、コメンテーターとして田中寛さんが、戦争の日常化により本質が見えなくなる危機を説いて、戦争の記憶を再び取り戻し、再確認するための資料を提起した。
例えば『あゝ特別攻撃隊』(1964年)という連続テレビドラマの主題歌。橋幸夫の47枚目のシングルレコードで、同名の映画も1960年に公開された。少年誌に掲載された戦記漫画ブームやプラモデル、傷痍軍人など自身の記憶を織り交ぜて、「特攻」研究の現在として、研究書や小説などを渉猟し、高橋和巳と川端康成の交流と戦争を通した死生観の接点を示唆する。
残念ながら集会では時間切れで、より個別に展開するまではいかなかった。また、私としても川端康成はいわゆる『雪国』に代表される日本の美を描いたノーベル賞作家という一般的なイメージしかなく、川端文学に特攻体験がどう影響を与えたのか理解することはできなかった。これについては多胡さんが本にされているので(『生命の谺 川端康成と「特攻」』現代書館 2022年)、それで知るよりないだろう。

特攻隊が突撃前に送る電信を受信していた地下壕に降りていく。(You Tubeより)
特攻については、たとえ志願であっても強いた側と強いられた側があるということは忘れてはならない。今以上に空気の支配する時代に軍の方針に異を唱えることなどできなかった。
戦時中は特攻が「軍神」と崇められて、戦意高揚に利用された。いっぽう戦後は「特攻くずれ」、無謀な行為であり、「無駄死」「犬死」との誹謗もされるようになった。
「特攻」についてはこのような二重の側面がついてまわる。曰く「軍国主義の無惨な犠牲者であり、殉教者でもある」。この2つについてどちらの視点も欠けてはならないと思うが、果たして流布される表象は涙をさそう殉教者としての側面が多くはないか。
さらに大きな問題として「特攻」の効果は敵軍よりも、犠牲者を「軍神」へと正当化し「1億玉砕」の意識を日本国民に与えたことにあるのだろう。
視覚メディアの事例をみてみよう。特攻が始まった1944年の10月から、国策宣伝雑誌の「アサヒグラフ」では、特攻隊の記事は148号から178号までの間に特攻隊の記事が18回掲載(表紙は6回)された。また読者数は300万人だという内閣情報部のグラフ雑誌「写真週報」は16回掲載された(表紙は5回)という。(『特攻隊映画の系譜学』中村秀之 岩波書店 2017年)
ニュース映画の「日本ニュース」では半分の回数で取り上げられて、尺数でも21.8%を占めたという。そして瓜生忠夫の回想によれば、最初の特攻をおこなった敷島隊の映像が「国民の間に複雑で異常な興奮をまき起こし、少年を中心とする純粋な国民の間に感涙を流させ」ることになったという(前掲書 P.30)。
また、「神風特攻に感動し、戦争に協力しようとする具体的な動きが出ていた。(中略)戦費調達の国債購入のために長蛇の列をなしていた。特攻隊への感激が人びとを戦争協力に駆り立てていた」のだ。(『特攻隊員の現実』一ノ瀬俊也 講談社 2020年)
まさに、国を救うために、若者たちが命を投げ出していく有り様は多くの人々に涙と感動を与えた。しかし日本国家の「人柱」としての「特攻」を見ているだけでは、それを強いた国の有り様は見えてこないのではないか。
その意味で鹿屋市の戦争遺跡や知覧特攻平和会館などの施設は、当時の軍部の思惑や戦争継続の戦略、そして天皇の役割など、特攻という行為について、根本的に原因を探るような資料展示が欠けているように思える。
「特攻」あるいは特攻隊については多くの書籍や映画・映像作品があり、戦後多くの人が知ることになったのは、それらのメディアであろう。そのなかにはまさに「泣かせる」ものや「美談」に収斂されてしまうものも多いが運命や業のようなを含めて考えさせるものもある。
私が「特攻」について複雑な思いを抱いたドラマが、まさにそれで、それを紹介してこの文章を終わろうと思う。
西村晃という役者がいた。ドラマの『水戸黄門』の二代目主役も努めたことがあるのでご存知の方も多いだろう。彼は徳島航空隊の特攻隊員の生き残りであった。
このテレビドラマは、その西村晃を起用するという配役が重みを増し、また特攻隊という悲劇をブルーフィルムにして創作するという、屈折した行為が不可解でもあり、陰影を強調していた。細かい筋は忘れていたが、謎の殺人事件としてダークな雰囲気がしこりのように頭に引っかかっていた。
今回調べてわかったのだが演出は森崎東であった。彼は「黒木太郎の愛と冒険」(1977)という映画でも三国連太郎が演じる激戦で生き残った復員兵を登場させて戦友の墓の前で自死するエピソードを盛り込んでいる。
西村晃が演じる初老の男・深沢は、ブルーフィルムと呼ばれる非合法の成人映画を自主製作しており、前科一犯の犯罪歴を持つ。特異なのは、そのブルーフィルムが「特攻隊の若者が、桜の木の下で、女学生と行為をする」という内容のものただひとつであり、しかも、全く同じ内容のものをキャストだけ変え、定期的に製作し裏市場に流通させていること。その作品はマニアの間で「マリア物」と称されるほどであった。(中略)桜の木の下で女学生を抱いたことは事実であるが、特攻兵のためなら体を捧げてもいいという女学生に対し、自身を特攻兵と偽りだまして行為におよんだのである。(中略)そして、その製作過程において、ふとしたことから女学生役の女優を殺してしまい…(<レアすぎる渥美清の刑事ドラマ『田舎刑事 まぼろしの特攻隊』を見た>より)
https://dear-tora-san.net/?p=50
ややもすると「特攻死」が無惨な悲劇から美談や感動の逸話として回収されてしまう傾向があるが、実態としては人間の生(いのち)への欲望や願望があっただろう。それを探るには想像力が求められる。
(本田一美)

電信を受信していた地下壕。(You Tubeより)

鹿屋市が作成した戦跡マップ
ABC企画委員会
http://abckikaku.web.fc2.com/
鹿屋市に残る戦跡
https://www.city.kanoya.lg.jp/kankou/bunka/bunka/bunkazai/senseki.html