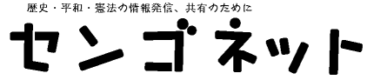政党と政治はどこへ向かうのか。ネットの影響と護憲・改憲の意味

講演する五野井郁夫さん

全国の選挙当選者図を映して語る
12月8日に北千住の千住介護福祉専門学校講堂にて「第19回憲法カフェ」が開かれた。政治学者の五野井郁夫さんを迎えて「選挙結果から日本の政治を考える」と題する講演があった。主催は千住九条の会。
「選挙結果から日本の政治を考える」
現実主義の人は国際秩序が危ないというが、東アジアの安全保障の危険性は、今日では冷戦の時よりも格段に下がっている。ただ、現実に合わせて理想を削るのは愚かであり、国際秩序を9条に合わせていくべきだ。
選挙を経て見てみると、政党の支持率で組織政党は低下した。維新については関西のメディアを支配しているので大阪では独占状態。
国民の半数は自民党の過半数割れは良かったという。これはすべての年齢で共通している。野党の選択について、野党共闘を期待しない人は半数であった。これはマスコミがマイナスイメージを付与した結果だろう。これ自体を与党は喜んでいる。野党共闘を恐れているのだ。
国民が何を望んでいたかといえば、景気対策であり、政治改革、政治とカネは多くはなかった。
国民民主党はなぜ善戦したのか? 国民民主は20~30代がボリュームゾーンで、「若者をつぶすな」との宣伝も、玉木代表は「ネットどぶ板選挙」と表現していた。ソーシャルメディアを見ている人に支持者が多い。これは自民党や立憲民主党とは真逆である。
国民民主の支持者はガソリン、電気代の値下げ、減税など生活に直結した要求で、手取りを増やしたいとも望んでいる。学生バイトなどの年収上限の103万の壁の引き上げを訴えた。そもそも先進諸国で学費が無償でないのは米国、日本ぐらいなのだが…。これは経済界に向けたアピールでもある。そして、支持層は自民にも立民にも入れたくないという第3極だ。
国民民主は希望の党の騒動(2017年)で誕生し、電力総連などが支援している。改憲にも意欲的で、議員の任期延長などの緊急事態条項を追加しようとしている。
東京都知事選挙でも、メディアはネットへシフトしていた。23年のデータでは、テレビを見てる時間は10代で36分、60代では257分だった。なお10代では新聞はゼロで、ネット時間は258分であった。
街頭演説で石丸と蓮舫を比較すると、蓮舫は30回、石丸は289回でライブと録画を拡散させるために、リアルの露出を増やした。無党派層は小池よりも石丸に投票した。
都知事選の石丸伸二の支持者は半分がyoutubeを参考にしている。その動画はクラウドワークスなどの募集で、動画で利益を得たい人が集まり、それによって石丸の切り抜き動画が拡散された。いっぽう新聞を参考にした人は蓮舫に入れていた人が多い。
現在の状況について、情報の摂取は趣味・娯楽は圧倒的にネットにアクセスしている。外国に比較して日本ではフェイクニュースが広がりやすい。それは外国と比較してニュースに対する信頼度が異常に高い。
ネット、SNSでイメージ政治が強化された。ここでは嘘をついても問題にされない、メディアで批判されてもネットで人気を博せばオーケーとなる。ただこの手法はリベラルでは使えない、行為自体が問われる。
石破政権は少数与党で運営は慎重にならざるを得ない。国民民主の玉木代表は軽い存在ではあるが、自民との連立には慎重になるだろう。立民は自公が退潮したから伸びたが、立民そのものへの支持は増えてない。薄氷の上にあるといえる。
護憲と改憲の動向だが、立民の枝野が憲法審査会の会長になった。元々は改憲論者なので注意が必要だろう。
右派にとっての改憲の本丸は憲法9条よりも、憲法20条、24条にあるのではないか。24条については、改憲案は明治時代の家族観に戻すことにある。これは日本会議の意向だ。神道政治連盟は20条を変えて、神道国家にしたいのだ。
酒井哲哉「九条=安保体制」によると、9条を維持する限り、重武装ができなかった。国際情勢と国内問題とを考えてリアルな経済的、倫理的な問題点を伝えていくべきだろう。護憲派の考えは実は理想主義だけではなく、現実的なものでもあった。
(文責編集部)