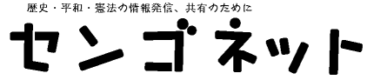戦後のヒロシマで「平和」を描き書いた!表現者四國五郎
元NHKディレクターで武蔵大学教授の永田浩三さんの話を聞いたのは2022年の4月だったか……。そこでは敗戦直後の広島における反戦の表現・言論活動の具体例として峠三吉と四國五郎の「辻詩(つじし)」を紹介されたのだった(辻詩ついては後述。また、このサイトの記事参照)。https://wp.me/pbla6S-SN
峠三吉は「にんげんをかえせ」で始まる『原爆詩集』で有名だが、四國五郎については今ひとつ知られていないのではないか。永田さんは『ヒロシマを伝える』 (WAVE出版 2016年)のなかで四國五郎の評伝を書いて、再評価も進んだ。そして御子息の四國光さんの書かれた『反戦平和の詩画人 四國五郎』で本格的な四國五郎の姿が描かれたと言えるだろう。
この本から彼の歩みを紹介したい。興味を持たれた方はぜひ、本書を手にとっていただきたい。
まず略歴だが、1924年に広島の貧しい農家に生まれ。小学校の時に家族で広島市に転居、画家になるのが夢だったが14歳で広島陸軍被服廠に就職、製靴の傍ら夜間中学に通っていた。1944年20歳で徴兵され、満洲・琿春へ、敗戦後はシベリアへ抑留された。ここが転機となった。
シベリアに抑留者され、その過程で収容所の「民主運動」を体験する。それは必要な思考過程であり、成長であり。重要なものであり、戦後の世界観を形成するひとつの軸となり、梃となり、原点であったと書かれている。「民主運動」については議論があるが、ひとつの人格形成としてみることは必要だろう。
1948年に広島へ復員し、弟が被爆で死んだことを告げられる。このときに戦争というものを真に理解したのではないかと記されている。殺し殺される殺戮の連鎖、それが戦争の本質だと。翌年から峠三吉や文化サークルとの交流が始まり、反戦・平和の活動が本格化する。
占領下ながら、反戦を訴える『反戦詩歌集』に表紙絵と詩で参加。さらに朝鮮戦争(1950年)の頃から反戦反核の詩や絵をポスターのように街角に掲示する活動をはじめた。これが「辻詩」だ。残念ながらこれは継続・発展することはなかったが、しかし、現在ではバンクシーにつながるような社会的アートの先駆的試みとして貴重な活動だったといえるだろう。また、丸木夫妻の《原爆の図》全国巡回の出発点となった広島での展覧会(1950年)を支えていたのは、峠や四國ら「われらの詩の会」の仲間たちだった。
その後は広島のなかで旺盛な活動を継続した。1955年から毎年開催している「広島平和美術展」への参画。ヴェトナム戦争反対の作品を収録した『四國五郎詩画集 母子像』(広島詩人会議 1970年)の発行。山口勇子の『絵本 おこりじぞう』(金の星社 1977年)の出版など、そして広島の街をスケッチして残してきた。その軌跡は「市民の中」にいて、市民に向けて平和の活動をしてきた。2014年に四國五郎は亡くなった。その後は丸木美術館の展覧会など画家として注目が集まるようになった。
四國五郎にそのような生き方をさせたものはなにか「強いて言えば、自国民の自由を圧殺し敗戦へと無謀な戦争をおこなった天皇制ファシズムであり、物事の本質を理解できなかった戦中の私自身への反省です。」との信念を紹介している。
この本のはじめに書かかれている父の思い出の文章は、まさに今にも通じるものであり、至言であろう。
「戦争はあっという間にやって来る。気づいた時にはもう遅い。結局、戦争をしないためには、ちゃんと世の中のことを知り、選挙で『戦争をしない政府』を自分たちの手で選び取るしかない」
(本田一美)

四國五郎没後、丸木美術館にて「四國五郎展 シベリア抑留から『おこりじぞう』まで」(2016年6月25日~)が開催された。これはそのリーフレット(丸木美術館HPより)