戦時下の「日本の哲学」=天皇制国家のイデオロギーを体験する
東京都現代美術館で「ホー・ツーニェン エージェントのA」という美術展が開催されている(2024年7月7日まで)。
ホー・ツーニェンは、シンガポール出身で東南アジアの歴史的な出来事、思想、個人または集団的な主体性や文化的アイデンティティに独自の視点から切り込む映像やヴィデオ・インスタレーション、パフォーマンスを制作してきたという。出自はおそらく華人だろう、あいちトリエンナーレ2019にも出品していた。
シンガポールは1942年2月15日に日本軍に占領され、以後「昭南島」と改称されて45年8月まで支配された。日本軍はシンガポールの華僑が東南アジアにおける抗日運動の中心になっていると見なして過酷な弾圧を加えて、約5万人が犠牲となった。当然ながらホー自身にもそのような歴史意識が伝わっているだろう。
展覧会はシンガポールの歴史を探るものや、時間の観念を表すものなど多彩だが、ここでは戦時中の日本の「京都学派」を扱った作品に注目したい。

ホー・ツーニェン-エージェントのA-展覧会-東京都現代美術館(webより)

京都学派の四人の座談会の様子「ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声」(youtubeより)
その作品《ヴォイス・オブ・ヴォイド – 虚無の声》は、西田幾多郎や田辺元を中心に京都帝国大学で形成された知識人のグループ「京都学派」を主題とし、VRとアニメーションを用いた映像インスタレーションである。VRとはバーチャルリアリティの略だが、「仮想現実」や「人工現実感」とも呼ばれて、人工的に作り出された仮想空間を体験する技術を指す。
鑑賞者はVR体験のためのゴーグル・ヘッドセットをつけて座敷へあがり、座ったまま覗くと、それは1941年に京都の料亭、左阿彌の茶室で行われた雑誌『中央公論』のための「世界史的立場と日本」という座談会の様子だ。そこには哲学者の高坂正顕(1900〜1969)、西谷啓治(1900〜1990)、高山岩男(1905〜1993)、歴史学者の鈴木成高(1907〜1988)が参加している。その座談会の速記者が鑑賞者自身であるという、歴史の記録者であり客観的立場だ。
そのまま立ち上がると、そこには青空が現出し、SFアニメに出てくる(ガンダムのような)メカスーツロボットの一群が浮かんでいる。姿勢を変えて寝転んでみると、暗い監獄のなかに没入する。独房は三木清や戸坂の視点だろうか。京都学派の左派であるとも言われる三木清(1897-1945)と戸坂潤(1900-1945)は獄死した。
座談会の茶室の空は未来世界のようで、その底に監獄があり、まるで天国と地獄のようでもある。
このようなVRの空間体験で人は京都学派の思想と哲学を受け入れることができるだろうか。当然ながらあくまで茶室での会話では、日本的な歴史哲学のテキストの断片しか耳に入らないし、そこに見られるのはアニメとして仮想であり、アニメ絵を通しての現実である。その言説よりも、知覚できるのは京都学派とその派生した歴史としての記録の再現なのであり、そこであらたに未来のように追加されるのは空に浮かぶモビルスーツ軍団なのだ。これを体験する人は、ある意味ゲーム的な意識として受け止めるのかもしれない。

空にはモビルスーツの軍団が…。「ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声」(youtubeより)
![ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド──虚無の声(山口情報芸術センター[YCAM])](https://i0.wp.com/sengonet.jp/wp-content/uploads/2024/05/cde0168c8dbc4685377b885d764cc267.jpg?resize=773%2C528&ssl=1)
かがんで見上げると座談会の茶室が浮かんでいる。「ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声」(youtubeより)
京都学派と脚光を浴びた「世界史的立場と日本」とは何だったのだろう。ここはやはり、当時の状況をおさらいするしかない。
1930年代、昭和の大戦の直前と対中国戦争継続のなかで、「日本を〝盟主〟とする東亜(ひがしアジア)が欧米に勝利して世界に覇を唱えるようになるという〝見込的構想〟と相即するものであった」(広松渉)のが座談会「近代の超克」と「世界史的立場と日本」であり、京都学派の「世界史の哲学」という思潮であり、思念でもあった。
雑誌『文学界』の1942年9月、10月号に掲載された座談での作家たちによる「近代の超克」と、同じ頃に西田幾多郎と田辺元に師事する京都学派の四人の哲学者、歴史家の雑誌『中央公論』に掲載された座談(ともにその後、本として出版された)が、「知識人の戦争協力」と「おなじ指向性をもった思想形成作用」であったという(『日本とアジア』竹内好 ちくま文庫 1993年)。
竹内好によれば京都学派を<総力戦と、永久戦争と、「肇国」の理想という三つの柱の関係を、論理的整合性をもって説明しえた最大の功労者は、京都学派であった。ことにその四人の代表選手によって巧みに構成された「世界史的立場と日本」連続三回の座談会だった>(前掲書 203頁)と評価した。
他方、桶谷秀昭は「世界史的立場と日本」という座談会については<開戦の予言となつた。たいへん評判がよかったさうである><近代の「世界史」の展開構造の中に大東亜戦争を位置ずけたのは、おそらくこの座談会がはじめてであつたらう><歴史的自己形成としてのモラリッシュ・エネルギィが「永遠の今」あるいま西田哲学の「絶対無」に聯関するというメタフィジクがある><さういふ思考の体系が、「世界史」と国家、国家と個人の存在理由の聯関が、永遠に結びつく暗示において、多くの日本人を惹きつけたと思はれる>(『昭和精神史』桶谷秀昭 文藝春秋 1996年)ともいう。
なにゆえそのような力を発揮できたのだろうか。このあたりの事情を広松渉『<近代の超克>論』(講談社 1989年)から引いておこう。
広松は竹内好が「近代の超克」を「戦争とファシズムのイデオロギイにすらなりえなかった」と評価していることに異を唱えて。<当時における〝日本国民〟は東亜諸民族の「盟主」意識をもち、また「東亜の盟主」としての使命感のごときをもっていた。(略)一九二九年恐慌を境とした世界経済のブロック化が日本経済に深刻な危機をもたらし、円ブロックを形成するためには東亜への進出が〝歴史的要請〟であったかぎり、ここにおいていわゆる「広域経済圏」、日本の「生命圏」ということが意識されずにはおかなかった。(略)このような歴史的情勢のもとで、日本民族主義の心情的論理、「種の論理」(田辺元)の大枠を踰越(ゆえつ)しえない場合、東亜協同体を形成して、欧米列強と対決しようという願望的構想が生まれるのは必当然的であろう」「日米開戦という現実を前にして、しかも、従前インテリたちが恐れていた敗北の危惧を吹き払うかのような緒戦の〝大勝利〟に狂喜する雰囲気のなかで――永年にわたる対支行動や国内統制の強圧について、インテリたちがそれまでいだいてきた「やりきれなさ」や「不満感」を解消し、――戦争と国体を合理化しつつあらたなる決意を促すものとして、それは迎えられた>(前掲書 175~177頁)
日本の社会は天皇制ファシズムへと向かっていった。1933年の佐野学・鍋山貞親の転向声明、それが対支侵略戦争、ひいては対米戦争を合理化する論理が用意された。そして1935年には美濃部達吉の「天皇機関説」が問題視され、戦争に批判的な思想運動や文化運動は抑圧され、1938年には「人民戦線事件」「唯物論研究会」への弾圧が続いた。このように左翼はもちろん、自由主義や反戦の活動は壊滅させられていたった。そのなかで京都学派の三木清は(転向左翼のありかたとして)、自由主義と共産主義、独伊の全体主義を乗り越えようと「協同主義」を提唱していた(結果として治安維持法違反として投獄されるのだが…)。
ここでは左翼の転向について注意したい。「マルクス主義者が思想的に転向する場合は、彼にとって世界観の総体、価値観の総体が根底から転換するという一事実である」「要言すれば、マルクス主義を自覚的に放棄することは、西欧近代文明の諸思想・価値観プロパーを端的に踰越(ゆえつ)することとして当人には意識される」(広末)として東洋的なもの向かうことが蓋然的だという。
進歩的なもの、西洋的なものに失望して、東洋的なものに向かうことは今日に至るまで反復されてきた事象だが、それが必然ではないにしろ自己正当化、自国優越思想、民族排外主義へと結びつくことも幾度も目にしてきた。
三木清の場合は八方塞がりの状況のなかで、なんとか自律的、主体的でありたいと行動した結果であろう。往年の左翼インテリたちも参加していた近衛文麿の「昭和研究会」への加入についても「現実の問題の解決に能動的に参与することがインテリゲンチヤにふさはしいことである」(前掲書 141頁)と三木は表明している。これは事大主義や「空気を読む」という言葉では説明できないものを含んでいるように思う。
話を「世界史的立場と日本」に戻せば、この京都学派四天王は、師匠である哲学者の西田幾太郎と田辺元の「日本の哲学」を敷衍するかたちで論陣をはり、海軍にも政策提言をしてブレーン的な役割を果たしていたという(『日本とドイツ二つの全体主義』仲正昌樹 光文社 2006年)。それが現れたのがこの座談会なのかもしれない。
ほんらいならば、ここで天皇ファシズムや大東亜共栄圏を正当化する言説の元となった西田哲学の評価や検討にも筆を進めたいところだが、あいにく筆者にはその力量や知識はない。上記の本による解説を引いておこう。
<西田は、西欧近代哲学の文脈にある程度乗りながら、西欧近代が封印しようとしてきた神秘主義の伝統を―それほど気負っている様子もなく―掘り起こしつつ、自らが志向している宗教的世界観に向かって次第に進んでいく(略)「真の無の場所」あるいは「絶対無」という極めて仏教的な概念装置を導入する。>そして西田を中心に京都学派が形成され<西田によって発見された「絶対無」の論理を、[西欧=近代]的合理主義を超えるものとして歴史的に特権化し、国家総動員体制をイデオロギー的に支持するようになった。>
西田の哲学は<〝日本〟という共同体(幻想)に完全に取り組む、全体主義の論理を正当化するうえで便利であった><天皇の身体に象徴される『国(家共同)体』と一体化することによって、西欧的な『理性の主体』としての狭い思考の枠に囚われ利己主義(我執)に陥っている『私』を、『理性』という名の桎梏から解放する>(前掲書 170頁)という論理を導き出した。
当然ながら西田幾多郎自身も大東亜共栄圏を支持してこう語る。「皇室は単に一つの民族的国家の中心と云ふだけでない。我国の皇道には、八紘為宇の世界形成の原理が含まれて居るのである」(「世界新秩序の原理」より『西田幾多郎全集』第十二巻 427~431頁 広松渉『<近代の超克>論』より重引)
以上、京都学派とそのバックボーンとなっている西田哲学について探ってきた。やはり三木清にせよ、田辺元にせよ、高坂正顕にせよ大もとは西田幾多郎であろう。
それについては、「近代ヨーロッパ哲学の超克という課題」意識から、西欧流の「有」の哲学に対して東洋流の「無の哲学」対置し、既成哲学を超えることを目指したことは、独自なものだといえるだろう(広松渉『<近代の超克>論』)。
余談ながら、西田幾多郎はマス・メディアによって「日本の哲学」者のスタアにされていた、と推測している。それは西田哲学についての評価とはまったく別の話である。戦中の西田幾多郎とそのイメージとして「西田幾多郎は戦時にあっては否応がなく時局・政治と関わらざるをえない立ち位置にあった。」「西田哲学が理解されていたという話ではなく,あくまでも西田幾多郎あるいは『善の研究』といった固有名詞が,ある程度広く知られていた状況にあったということ」(<偽史言説としての『西田幾多郎全集』(1947年)購入徹夜行列>松井健人 東京大学学術機関リポジトリ)は確認しておきたい。
日本は80年代に「ジャパン・アズ・ナンバーワン」「日本的経営」が讃えられ、ハブル時代を謳歌した。それによってかつての東洋の盟主としての意識が復活したのではないか。西洋に対して東洋を対置した場合。朝鮮や中国はどう位置づけられたいたか、振り返りみておきたい。それは帝国主義意識と言ってもいいだろう。さしあたり韓国への植民地意識やそれに対する無理解、中国については靖国神社閣僚参拝問題への対応などを指摘しておきたい。
しかし今、日本は将来不安に苛まれ、あらたな戦前だとも巷間伝えられるなかで、戦争をできる国にしたい側はナショナリズムの言説を盛り上がるし、「日本スゴイ」の掛け声は無限に続く。だから「日本」のアイデンティティや日本の優位性を強調する言説に警戒が必要だろう。そして、戦前の「日本の哲学」をもとにした京都学派や「近代の超克」の思考がそのままのかたちで復活することはないにだろうが、歴史意識が困難になっている状況ではある。だから、かつての京都学派の役割を確認することになった。
(本田一美)

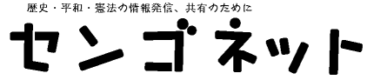
![ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド──虚無の声(山口情報芸術センター[YCAM])](https://i0.wp.com/sengonet.jp/wp-content/uploads/2024/05/580fdd2d25fdfe3727b823ed673b1fb2.jpg?w=307&ssl=1)

