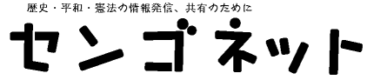防衛費増大は民衆の生活を圧迫する 経済の軍事化を阻止しよう!

会場は多くの参加者で埋まった
2月21日に<「新しい戦前にさせない」連続シンポジウム>の「税金で育つ『死の商人』 武器で平和は創れない」という集会が、東京・文京区民センターで行なわれ纐纈厚さん、望月衣塑子さん、小野塚知二さんが登壇した。3名の講演後にシンポジウム、質疑応答があった。主催は共同テーブル。
明治大学国際武器移転史研究所客員研究員の纐纈厚さん(山口大学名誉教授)は、日本が侵略戦争の拡大と同時に武器の生産・輸出の増産の歴史を報告し、戦後の朝鮮戦争以降、再び拡大していく現状と危険性を指摘した。
望月衣塑子さん(「東京新聞」記者)は、政府が2014年に武器輸出3原則から防衛装備移転3原則に転換し、さらに安保3文書が閣議決定され、重工業大手の三菱重工・川崎重工・IHIなどの武器生産企業を潤わせていること。国家予算が軍事という無駄金に使われていることを批判した。
小野塚知二さん(東京大学名誉教授)は、日本の政・官・財の癒着として経済の軍事化する問題点と転換を示唆をした。ここでは小野塚さんの講演を紹介する。

左から望月衣塑子さん、小野塚知二さん、纐纈厚さん
■小野塚知二さん(東京大学名誉教授/放送大学客員教授)
公共事業はマイナスのイメージがあるが、公共財の整備・景気対策の機能がある。ケインズ主義という政策は一時的なものだったが常態化する。政・官・財が結びつき軍事に依存しないと再生産が成り立たなくなる、それにより自由や民主主義への制約が増える。安倍政権で経験した。
日本の公共事業を振り返ると、日本では東京下関新幹線構想(1930年末)、東京オリンピック(1940年予定)があり、ナチ・ドイツではアウトバーンがあり、米国では大規模土建工事(1930年代)があった。今の日本でもマイナンバーや東京オリンピック、大阪万博、リニア新幹線、半導体産業への投資なども公共事業。
戦後の日本軍備は米軍規格に再編されたが、掃海艇など艦船は国産となった。イージス艦はシステムが米軍なので、そこは分からない。戦車は日本製、航空機は禁止されていて、国産化したがF16日米共同開発。航空機搭載兵器は基本米国製。
航空機は日本生産は頓挫した。主力戦闘機の日英伊の共同開発の計画がある。今は米国の属国なので、兵器の国産化は限界がある。日本は米国製兵器・航空機の最大の市場。日本製兵器は公共事業化している。日本製兵器の評価についてはオーストラリアとインドが興味を示した。
抑止力の議論は見誤っている。相手がどう見るかということ、攻撃をおそれているのか、そこが問題となる。ロシア、中国や韓国に対してそれができいていない。
軍事より普遍的公共性を世界に貢献したほうがいい。日本国憲法、食文化、宮崎駿などのアニメ・サブカルチャー、薬物・小火器に脅かされない安全な社会。健康保険制度。
工業製品を輸出して外貨を稼ぐシステム:投資主導経済政策から脱却すべき。日本人が貧しいので転換が必要。国民が消費できるように「消費主導型」にしていく。たとえばベーシックインカムなどを導入してもいい。
民衆が富むということ。江戸時代はあったが、近代以後は国富となり民富が失われた。現在は炭素魅了型経済システムの「社富」思想と食料・農業システムの問題点。「民富」思想の再定着を……。
(文責編集部)