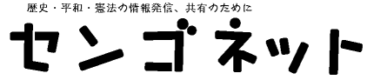沖縄民衆の「生と性と基地」をみつめる 映画 『モトシンカカランヌー』
第10回ねりま沖縄映画祭2025が「わたしの沖縄 あなたの沖縄」と題して練馬駅周辺で、10月11日から11月24日まで上映・開催された。そこでは伝説的なNDU(日本ドキュメンタリストユニオン)の作品である『アジアはひとつ』と『モトシンカカランヌー』が上映された。
近年、日本へ復帰直前の沖縄の情況や観光とは別なダークな面に関心が寄せられている。そんなもうひとつの沖縄に焦点をあてた先駆的な映画が『沖縄エロス外伝 モトシンカカランヌー』だ。上映当日は約90名の参加者があり、上映後は小野沢稔彦さんのトーク・質疑応答があった。以下当日配布されたレジュメを紹介する(その後、加筆・訂正)。

映画『モトシンカカランヌー』(ねりま沖縄映画祭フェイスブックより https://www.facebook.com/nerimaokinawaeigasai)
——————————————————
第10回ねりま沖縄映画祭 レジュメ 小野沢 稔彦
この映画は「ナオミ」という沖縄のどこにでもいて――特に米軍基地にへばりつく(従属する)ように――そして沖縄のどこにも存在しない不在の「女」をめぐるドキュメントである。そのことを通して沖縄(特に戦後史)と我々とを問う映画。
「NDU」の映画はこれまで、我々の「政治」的環境のなかで、「政治」主義的に観られ、語られてきた。しかし、大阪万博(このことは「人類館事件」を問いかえすことになる)と<コザ暴動>から50年の年に当って、改めてNDUの『モトシン』を観ることは近代「日本史」の内実を問い直させる。この運動の映画は、単に政治的環境のなかで生まれた政治的映画ではない。この映画はこうしたイデオロギー的観方を超える真の今日的運動の映画である。沖縄における民衆「生」のあり様の多様な営みと「政治」性とが密接に結びついた沖縄の現実を問い直す――我々の今をも――<全体映画>であることを想起したい。そのことはこれまでこの映画を観てきた我々のこの映画に対する「観方」をも全面的に問い直させるものである。
このことは同時に、映画(特に沖縄についての)を<作る>方法への問い直しにも繋がるだろう。
映画はまず前半部で、表層的な、あるいは復帰を前にした主流的な政治情況(民衆の生の具体性をも)を問う。『モトシン』はともすれば<ナオミ>の生のあり様のみを描いた特異なドキュメントと思われがちだが、<ナオミ>へと眼を向けるに至る政治・経済・文化情況をまず映画は見ている。
すなわち、全軍労――戦後沖縄を軍事支配する米軍との直接対峙。そのことは戦前には「日本軍」への従属(そして現在の自衛隊)を沖縄の目指す方向性とした、この闘争の意味と困難さをさぐる。戦うことは自己否定すること――首切り反対闘争。同時に占領観光の現実を中心とする地域経済と軍事の繋がり。ドル買い(占領経済と民衆)。その観光――とヤマトの労組を中心とする復帰運動、基地経済に依存する大衆の経済情況。同時に映画はヤマトの沖縄への視線をも暴く。すなわち、総評の男性組合員の「買春」発言。また、女性組合員の観念的で高踏的発言(このような女性…)にも注目すべきだ。
同時に、近代以前の沖縄が東北アジアとの全的交流のなかで「沖縄」であったことの記憶も消えているわけではなく、天皇帝国・ヤマトへの帰属政治は問われ続けており、その運動性が、日の丸復帰運動への抗いとしてもある。そうした全体の光景がこの映画ではまず、表象する。特に経済生活を営む民衆のふてぶてしさはやがてナオミの生に繋がるだろう。
それ以上に『モトシン』の描き出す表層的「復帰運動」の裡には、戦前・戦中・戦後の「日=米」沖縄抑圧政策の内実、戦前の天皇制、戦後の日の丸復帰願望でしかない「ナショナリズム的」限界をもったヤマト=沖縄の戦いの限界をも問い直さなければならない課題が浮上する――勿論、戦中の「日本軍」と戦後の「米軍」の暴力的弾圧下で、世界的に見ても例外的な激しい民衆闘争はあり、その内実をノスタルジックに語るのではなく現実運動を再評価すべきだ――戦後の「命どぅ宝」闘争など。
その上に『モトシン』は、そうした制度内性内包する限界を突破する方法をどこに求めれば良いかの困難な問いを建てる。
そして「NDU」によって実践されたのが、沖縄民衆の心性底流に生き続けている<辺境>的な生に眼を向けることであった。すなわち「近代的制度内」的闘争が忘れようとした――当時ヤマトで流行した――<辺境最深部>へ向って退却せよ!という
こうしてNDUは、沖縄民衆の生の根底部に生きる<モトシン>の民衆に眼を向け、その生の有り様を共に棲みきるなかから見つめようとする。例えば小説『沖縄の少年』が描き出す現実こそは民衆の「生と性と基地」につながる。こうして<性>の深部にNDUは下降し、その抑圧された<性>のなかに色濃く映し出される<政>の課題へと向きあうことを我々に要求する。<性の>のなかにある<政>とは、『沖縄の少年』が表象する世界であり、軍政下の沖縄の民衆の内面そのものの「世界性」である。更にはコザの街に生きる民衆の内面を形成する「チャンプルー文化」であり、典型的には「沖縄ロック」に表れる――「コンディション・グリーン」たちのパフォーマンスの持つ戦闘性もまた、コザの性と疎外された黒人文化のクレオール文化であり、こうしたことに眼を向けることで、始めて「日の丸」に依存する政治の文化の限界を突破する運動は拓かれる。またナオミの唄うワイ歌の民衆性も文化運動である。NDUの辺境最深部への退却はその1つの方法である。性の政治性は戦後における米軍高級将校の性政治をも撃つだろう(それだけでなく日本軍のそれをもを)。
さて、NDUがモトシンのこの世界へ下降するのにどんな方法=実践を行ったのだろうか。
すなわち、ヤマトのヤワな学生中心の映画人はどのようにしてモトシンの世界にたどりついたのか――それは、自らを表層の政治性から離れ<モトシン>として、<自らを演ずる>ことによって、モトシンのなかに同居することを行ない、このモトシンを演ずる擬態を自らドキュメントすることで、<撮る>、という一方的関係性を反省的に見つめるのだ。
モトシンを演ずる――このなんともいいかげんでただグダグダとナオミたちと酒を呑み、無為の時間を共有すること――ナオミたちの24時間は総て、政治性によって奪われた無為の時間だ――によって、NDUもモトシンでしかない擬態となり、それを撮る。こうしてNDUは、世界で始めてモトシンの生を表象する。周縁から政治の中心を見つめ直すこと。
モトシンの世界――そこには、ヴェトナム戦争の最前線で「死」を強要されている黒人兵のせっぱつまった怒りと恐怖がつみ重なっている――この時、沖縄に進出したブラックパンサーはまだ<女>性の抑圧された情況に眼はいっていない。
モトシンの世界――そこには沖縄の制度的戦いから弾き出された、無名のモトシンたち、すなわち周縁を生きる民衆の政治的抑圧情況への声なき怒りがつみ重なっている。そして同時に、彼らの内面の政治言語に固定されない恐怖と怒りとは、集団的マグマの時間のように噴出する――モトシンの撮る暴動――黒人爆発――は予兆となって、やがて<コザ暴動>へと連動する。最も差別され、世間から無視された者たちの声にならぬ生のなかからこそ、世界への反逆は建ち上がる。やがて起こる「コザ暴動」を前に、コザ市中では健全な「市民」たちと米軍(白人将校の妻子たちを中心に)とが――今日では離島を中心に沖縄各地で自衛隊と「市民」によって――沖縄に独特な音とリズムのなかで民俗的「祭り」をくり廣げるが、「市民」から排除された「モトシンカカランヌー」と黒人兵は、その祭りに加わることはない。沖縄の官民・米軍とで虚構される熱量をNDUのカメラは冷たく突き離して見つめる。
コザ暴動、それは無名の民衆、すなわちモトシンカカランヌーたちの「政治」を超える内面の噴出である。その現実性を制度内的人間は感知しえない、どんな人間が中心になっているのか、そしてなぜこの時に起こったのか、などという制度的世界の言説を超えて、民衆暴動は、『モトシン』たちの言葉にならない共同の心性の裡に準備され、突出したのだ――映画『モトシンカカランヌー』はその告知である。
そして、NDUの民衆の怒りの最深部へと降下する方法とこの映画は、改めて見直さねばならない。