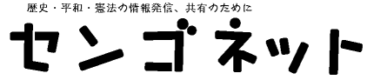日本人はいつから中国と中国人を蔑視してきたのか

『團團珍聞』(1879年6月21日 113号)日本と中国が文明のウォーキングマッチをしている絵。日本は急いで近代化し、大きな図体(清国)で足下がおぼつかないと馬鹿にされている(小松裕「近代日本のレイシズム」より)
高市政権への支持率が高いという。なぜ支持率が高いのかは複合的なものだろうし、マスコミやSNSの影響もあるだろう。人気の理由のひとつに「外国人政策を厳しくする方針に期待する」というものがあるが(―沖縄の米軍基地に適応してほしい)、これは端的に排外主義的な風潮に乗っかったもので、倫理的に問題があるだろうし、なにより日本国憲法前文の精神にも反しかねない。
また、日本が「台湾有事」について軍事介入すること(集団的自衛権の発動)がありうると明言した高市の国会答弁(2025年11月7日)は、日中関係を一挙に悪化させている。これに対する国内での批判は弱く、むしろ答弁を引き出した立憲民主党の岡田議員をなじるものがあり、高市発言を評価する声も聞こえてくる。
このような反応については、戦前、戦後を通じて日本社会が外国人に対して、一定程度に距離を取り、差別・排外を続けてきたことを振り返れば特に驚く話ではない。私の記憶でも外国人を「ガイジン」という言葉で一括りにして排除し、その排除された当事者自身も「何年住んでも永遠によそ者として扱われる」との意見がある(見田宗介の『社会学入門』に、日本人になりたいと米国から来日した若者が、結局のところ日本人になれなくて帰国する話が描かれている)。
そして、欧米人とアジア系の人間にも対応に差がある。日本には明治以来、日本国家の方針として「脱亜入欧」が母斑のように張り付いている。西欧文明=近代化とし、そこからアジアに対して差別・優越意識を持つようになる。それが今日まで続いているのが現状ではないのか。
しかし、例えば江戸時代には朝鮮半島との善隣友好と文化交流のため朝鮮通信使(1607年〜1811年に12回)が派遣されたし、中華(中国)についても古来より文化を輸入し、漢籍を教養の必須・基本としてきた。いっぽうナショナリズムの源流も出てきて本居宣長などの国学者が日本の優位を主張する考えもあった。そしてアヘン戦争(1840-42)により、力の論理という現実を突きつけられた知識人たちの一部は、中国を古い秩序の国とみて中華(華夷思想)からの離脱を促すことになった。
日本の支配・知識人層の中国認識だが、共通しているのが、中国には国家観念がない、公共観念がない、個人の利益、私利の追求のエネルギーがすごいということだ。近代の国民国家の「国民・国家意識」から批判的に見るのが一般的であった。このような見方から、統一した国家形成ができないので容易に外国から支配を受ける、その前に日本が…ということになる(小島晋治『近代日中関係史断章』岩波現代文庫 2008年) 。それが満洲国などの傀儡国家の形成へとつながっている。
他方で日本の民衆の中国・中国人観はどうなのだろうか、社会的意識や感情をきちんと分析したものはそう多くない。金山泰志の『近代日本の対中国感情』(中公新書 2025年)では戦前の少年雑誌や大衆文化が中国や中国人をどう表現してきたか探索している。これを手がかりに考えてみよう。
その前に、『銀の匙』という小説をご存知だろうか。1913年、1915年に東京朝日新聞に掲載された中勘助の自伝的小説で、幼少期の日常を綴ったものだ。その一部に、日清戦争が始まり「戦争が始まって以来仲間の話は大和魂とちゃんちゃん坊主の話でもちきっている」として、学校でも先生が朝鮮征伐などを話して、ナショナリズムに傾いていく情景が描かれる。「弱虫はみんなちゃんちゃん坊主にされて首を斬られている。」と作家である主人公はその見立て遊びに憤然とするのだが、子どもの戦争ごっこや大衆の状況を知ることができる。
ちゃんちゃん坊主とは、満州族の風俗である頭髪を指す清国人のことだが、江戸時代に中国風の服装をして、町中で鉦をちゃんちゃんと叩きながら飴を売り歩いていた者の音から出た語ともいわれ、それが転じて「支那人」自身を意味する言葉になった(金山泰志)。小松裕によれば<「ぱっち坊主」や「芥子坊主」と呼ぶのは江戸期に始まる。しかし、そこに侮蔑的な意味を含まれておらず、単なる呼称に過ぎなかった>(小松裕「近代日本のレイシズム」文学部論叢 78 43-65, 2003-03-20 熊本大学)という。

『團團珍聞』((1879年2月22日 96号)琉球処分を先取りしたもの。包丁で切って与えられようとしているのが「琉球芋」で、豚(清国)がそれを食べようとしている(小松裕「近代日本のレイシズム」より)
それがアヘン戦争の敗北以降は変わってくる。1870年(明治3)には『西洋道中膝栗毛』という本が明治初期の「文明開化」の雰囲気を背景に、西洋文化に触れる主人公たちの珍道中をコミカルに描いている。そのなかに<「支那学士」に「ちゃんゝ ぼうず」とルビがふられている>という。そして、1874年(明治7)の『東京日日新聞』の記事には「チャンゝ 坊主」が出ている。さらに絵入りの風刺雑誌の『團團珍聞』では、いくつか記事が掲載されている。<民衆の中に中国(人)=「豚」のイメージを植えつけ拡大するのに大きな役割を果たした>(『近代日本の対中国感情』)と小松は見ている。
こうみると「日清戦争前からすでにこのようなネガティブ描写はあった。壬午軍乱(一八八二年)や甲申政変(一八八四年)など、朝鮮半島をめぐる中国との緊張関係のなかで、戦争前から日本人の中国人に対するネガティブ感情は燻っていた」(前掲書)と見るのは妥当だろう。
そして日清戦争後、勝利への驕りから、敗者の中国人を「小ばか」「嘲笑」することが定例化していく。さらに小説などでは<戦争中の多くは、「敵兵」として表れていた中国人だったが、戦後は「悪人」として描かれることが多くな>り、<記憶を定着させる方法の一つに反復があるが、ネガティブな対中感情もまた、各種メディアで中国関係の事件が繰り返し語られるなかで、日本人のなかに根深く定着したことが考えられる>(前掲書)
さらに北清事変(義和団事件 1900年)、日露戦争(1904年)でも、中国に対するものが語りつづけられる。特に日露戦争では「満洲」に関心が寄せられた。日本では満蒙権益が対中政策の根幹となる。大正当時の人気雑誌『日本少年』(1906-1938)では、冒険小説が掲載されていたが、そこでは悪人として中国人が登場する。あるいはマンガでこっけいなものとして「嘲笑」の対象となった。

『少国民』1894年12月1日号 清戦争回戦以来、豚を解き放ち子どもたちが竹刀をもって追いかけて打つという遊びが日本各地で流行していることを伝える挿絵。豚を「支那蛮人」に似ていると説明している(金山泰志『近代日本の対中国感情』中公新書より)
満洲事変、日中戦争が勃発した30年代は雑誌『少年倶楽部』(1914-1962)が人気となっていた。そこでの時事解説記事では、日清戦争と違い「弱い」と見下した意識があった。それを象徴するのに「小癪な」「生意気」といった上から目線であり、その後くりかえし出てくる「暴支膺懲」(暴戻な支那を懲らしめる)というスローガンともつながってくる。また、中国人=悪人というイメージを定着させて、日本の対中侵略を正当化させた。

『少年世界』1895年4月1日号 日本の少年に降伏するという挿絵(金山泰志『近代日本の対中国感情』中公新書より)

「支那劇」という中国を舞台とする映画もつくられて悪人として描かれた。上は『幻の帆船』1925年 の広告。下は『七面鳥の行衛』1924年 のスチール写真。ここでは貪欲で滑稽な中国人が描かれる(金山泰志『近代日本の対中国感情』中公新書より)
このような民衆の意識は日本の敗戦で変わっただろうか、空襲を受けた日本国内はともかく、中国や南洋など「外地」にいた人々は、この戦争は中国に負けたとは思っていなかった。1972年の世論調査では、対中国戦争で「悪いことをしたと思う」は26.4%だったという(吉見義明『草の根のファシズム』東京大学出版会 1987年)。そこには「聖戦」感の残存、戦争協力反省の中断、アジア(中国)に対する「帝国」意識の持続があり、この意識・態度と最近の事態と深い関連があるという(吉見)。
もちろん現在の嫌中意識については、情報が更新されているだろうし、現在の中国からの影響が多いだろう。ただし、背後にある影響についてはいろいろ考えざるをえない。
今でもあからさまに「シナ」という言葉を使用している人がいる。過去の例を参照しているのは明らかで、当然ながら確信犯として意図的に使用しているのだが、一般的な言葉でも差別・侮蔑的意味で使用すれば差別語になるということを言っても、おそらく居直るだろう。
この本では<「支那」という言葉が使用されていた近代日本で「支那」及び「支那人」がどのように語られていたのかを総体的に把握することが、必要だろう・「支那」という言葉とともに、何らかの否定的表現や否定的評価が付随している>として、「支那」に「チャンチャン」にルビをふられている例を紹介している。
『銀の匙』に戻せば、主人公は日清戦争時の社会での戦意高揚や差別・排外主義の風潮を嫌悪し、反発をしていた。今は『銀の匙』の描かれた時代とは違うが、差別意識や反動的な抑圧状況に対して、主人公のように抗って皆の前で道理を主張できるかどうかが試されている。
(本田一美)