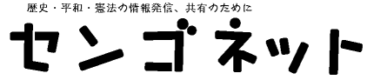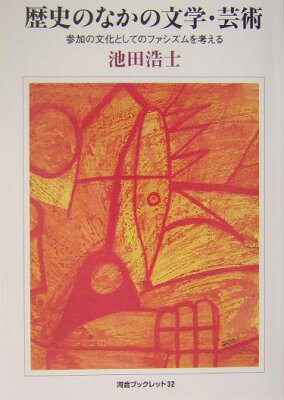戦時歌謡を聴いて過去といまを考える

講演する池田浩士さん
池田浩士「私たちは歌で戦争を支えた-民衆の自己表現、戦時歌謡-」
12月11日に東京芸術大学で「芸術と憲法を考える連続講座vol.24」が開かれた。「私たちは歌で戦争を支えた―民衆の自己表現、戦時歌謡―」と題して、池田浩士氏の解説を交えて戦前の日本の歌謡曲(戦時歌謡)を聴くものであった。主催は東京芸術大学音楽部楽理科(後援:日本ペンクラブ)、共催は自由と平和のための東京芸術大学有志の会。以下に講演要旨を紹介する。
お話: 池田浩士さん
(京都大学名誉教授)
1936年の日独防共協定調印以降の日独協調のなか、1938年9月にヒトラー・ユーゲント一行が来日して東京美術学校や音楽学校を見学したり、歓待して、ヒトラー・ユーゲントの歌、ナチスの歌、などを日独双方で唱和し、愛国行進曲の合唱、最後に君が代が斉唱された、と『萬報朝』が当時の様子を紹介している。『東京芸術大学史』にもそれが掲載されている。そして、北原白秋がヒトラー・ユーゲントの歌を作詞したり、藤原義江が歌っていたりしているのだが、そのことを嘆くとともに時代のあり方を確認したい。
これから聴く曲は結論を語ってかたがつくものではないので、ともに聴いて感じて考えたいと思う。
1>『愛国行進曲』1937年12月発売
当時、この曲はレコードが100万売れたという。1937年に支那事変(日中戦争)が勃発したが、この歌は戦争については触れていない。歌詞は「八紘」「皇国常に」など、限りない日本の自己賛美、自己肯定、天皇しかない、ということを謳っている。
2>『日の丸行進曲』1938年4月発売
紀元節、明治節、天朝節、神武天皇節という節がありましたが、この歌にはそのうちの3つが詠われている。この歌には、「去年の秋」「敵の城頭 高々と」という歌詞から、召集礼状で徴兵されて中国へ送られた兵士が主人公で、1937年12月8日の南京城に日の丸の旗を掲げたという物語が連想される。
3>『九段の母』1939年4月発売
さきほどの日の丸少年を謳った歌から、ちょうど1年後で、私はああ、彼もついに靖国神社に行ってしまった、という感慨を憶える。田舎から上野でてきて、靖国に向かうということが、母の立場で語られている。こんな大きな神社に祀ってもらって、勿体ないと念仏を唱えるという、普段の生活が出ていて、大きな神社とは無縁な民衆のあり方を描いているところにリアリティがある。
4>『大東亜戦争海軍の歌』1942年7月発売
「あの日旅順の」という日露戦争のことが出てくる。そのとき特攻隊を編成したことを受け継ぎ、「父母の血を継いで 潜った真珠湾」という表現がある。当時から人間魚雷で特攻隊を強制していた、ということを伝えている。
5>『日本よい国』1943年7月発売
「鍬を持つ手を 剣に替えて」ということで、いままで家族で土地を耕していたが、その道具を武器に替えて立ち上がらなければならない、そこで情景として桜の花が咲くと象徴化されている。
6>『桜花に誓う―女子挺身隊の歌』1944年7月発売
女子挺身隊という言葉は注意が必要。当時、1944年に14歳から25歳までの女子が女子勤労挺身隊として勅令が出た。朝鮮半島ではそれがない、だから政府はそれについての責任がないといっている。官斡旋方式でおこなわれたから自由徴募という業者による斡旋であったが、これは国家が後ろ盾となっている。これは強制連行となった。
7>『愛国の花』1938年4月発売
この作詞をしたのは福田正夫という大正デモクラシーを代表するような詩人であった。その人がこのような詞を書かかねばらなぬことの無念さがある。インドネシアのスカルノはこの曲が好きで、インドネシア語で歌わせたという。この曲は、戦後の日本とインドネシアの関係をも考えさせるものだと思う。
日本の蓄音機は29年から38年で176万台が生産されたという。これまでの曲は戦時歌謡(国民歌謡)と言われるもので、さまざまなメッセージが込められている。戦争がなければよかったのか。それを考えるときに、戦争は原因ではなく帰結ではないか、ということを押さえなければならない。
それは天皇と私との関係、それが大きい。天皇制を頂点とする日本の国家・社会が謳われていた。日本の文化だという人もいる。そういう社会のあり方が抑圧・支配の装置だった。そういうことが、これらの歌詞から見えてくる。結果として人々が殺されたということ。八紘一宇の手先として強いられた、内には抑圧支配、外に向かっては侵略の武器だった。しかし当時生きていれば同じような作詞をしていたかもしれない。天皇のために死ぬことを選んだかもしれない。
天皇と私の関係が強かった、そのことを考えたい。人間は独りでは弱いが、もうひとりの人と出会うことで大きくなる。その時に重要なのが表現の自由。表現の自由はもうひとりの人と出会うことで生かされる。
(文責:編集部)

愛国行進曲の冊子