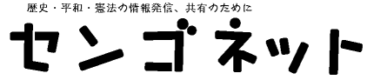尹大統領の戒厳令発令のニュースに反応した日本の類型

Xに投稿された井上アナウンサーの発言(xより)
https://twitter.com/Luckychan0105/status/1864230220485865821
韓国の尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領の戒厳令発令(12月3日)には驚かされたが、その後の経過は韓国民衆の奮闘により国会の戒厳解除決議、大統領の弾劾決議へと進み。尹大統領の職務が正式に停止された。今後は警察の捜査と裁判所の審理に移行するが、どうなるのかは不透明だ。
日本の反応だが、X(旧ツイッター)を見ているとTBSのニュース番組で「韓国ではまだ民主主義が根付いていないのかな」(Nスタ 井上貴博 12月4日)というコメントへの投稿を見かけて、あわてて確認した。テレビを持っていないのだが、youtubeでも流しているので見ることができた。確かに話していた。さらには「伊大統領が辞任して反日政権になると、ほくそ笑むのは中国であり北朝鮮であり…」と続くのである。これは番組のコメンテーターにレスを求めた発言だが、まさにネトウヨ思考となっている。
さすがに反響が大きかったようで、4日の発言について自身がキャスターを務める「井上貴博 土曜日の『あ』」(12月7日)の番組内で釈明をしたようだ。
「非常に軽率な発言でした。強く反省をしています」「韓国の民主化の経緯、歴史とか、知識、認識、これが足りなかったというところを自分自身、痛感しました」などと語った。(Yahooニュース 12月7日)
多数の批判が殺到して、弁明せざるを得なくなったのだろうが、どうやら「民主主義…」の部分だけを反省して、「反日政権になると…」のくだりには触れていないようだ。
そもそも日本が韓国に対して反日、親日とレッテル貼りをしているところが問題なのである。意味不明な優越的な立ち位置はなんなのか? そういった思考停止状態はいつからなのか。日本には「嫌韓」はあっても、相手を知ろうとする「認韓」はなさそうだ。その起源は遡れば豊臣秀吉のあたりまでいきそうだが、ここでは近代に絞ってみてゆきたい。
原朗氏によれば日清・日露戦争は戦争の目的が朝鮮の支配であったとして「第1次・第2次朝鮮戦争」という名称を提唱している。そして日清戦争の直前に日本軍は漢城(ソウル)の王宮を占領、武装解除する(朝鮮王宮占領 1894年7月23日)。
その端緒となった様子をみると、日本軍は仁川に上陸し待機していた。「外務省から派遣された本野一郎参事官が7月20日、部隊を率いる大島義昌混成旅団長を訪ねてきた。
清国兵を撤兵させろと朝鮮政府に要求し、その回答の期限を23日に設定している(略)要求が受け入れられない時は、政権を交代させたいので、王宮を包囲して軍事力で脅してほしい。そのために清国軍と戦うために南下するのをしばらく待ってほしいという要請であった(略)悩んだが親日政権ができれば、その後のソウルの警護や物資運搬も楽になると判断し、受け入れた」(『歴史認識日韓の溝』渡辺延志 ちくま新書 2021年 146-147頁) これは、日本陸軍の『日清戦争史』の草案だが、事実だが都合が悪いと差し替えられた。
以上のようにかつての「親日」とは武力によってつくられたものであった。その後は韓国併合(1910年8月22日)へと進んでいく。「1904年2月10日の日露戦争の宣戦布告から2週間もたたない2月23日、日本は(略)軍事上必要な地点を日本が収用することを認めさせる内容を含む「日韓議定書」を押しつけ、(略)韓国の軍事・外交・財政・交通・通信などを日本の監督下に置くこととします(略)実際には日露戦争の時期に日本は韓国支配をほぼ決定的にしていたわけです」(『日清・日露戦争をどう見るか』原朗 2014年 NHK出版)
日本の状況はこれらの認識が一般的だとは言い難い。かつての「明治政府の対外政策の基本的な姿勢は、欧米には徹底的に丁寧に、朝鮮と清国に対しては徹底的に弾圧的に」(原朗)という態度が今日どれほど変わったのかは疑わしい。
要するに「親日」とはあくまで、日本の意向に沿うもので、それは日本に従うものとして認識されている。韓国が自国の立場を主張したり、意に沿わない対応を取れば、それはたちまち「反日」となる。
安倍政権以降、自民党の一部はネトウヨと親和的だったが、それが政権の長期化で社会全体へと広がったのではないか。マスコミも例外ではない。政府発表に依存して情報を垂れ流すという、「官報」スタイルができあっている。これに対抗するのがジャーナリズムだが、それがない以上、TBSのアナウンサーのような政権の意向を忖度する発言が出てくるのも当然なのだろう。
それにしても、その不用意な発言が図らずも、日韓関係の日本の不都合な立ち位置をあきらかにすることとなった。そして、SNSの効用というのも結構あるなと再認識した。
(本田一美)

Xには井上アナウンサーの発言を揶揄・批判する声が多数投稿された(Xより)
https://twitter.com/nextan/status/1864830878154969279