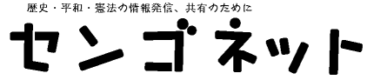子どもから大人へ。軍隊や戦争を育むものはなにか
サビーネ・フリューシュトゥック 人文書院 (2023)
自分の幼児時代の体験を振り返ると、争いごとなどは忌避する傾向にあったと思う。幼稚園で乱暴な子がいたりしたが、理解できなかった。
それでも、ある程度年齢が進むと、陣地取りゲームのような遊びに加わることもあったが、力も弱かったこともあり、自からやりたいとは思わなかった。
子どもは本質的に戦争に魅了される、とこの本の冒頭にあるが、この仮説は間違いだろう(著者自身はそれを紹介しているだけだが…)。ただ社会のなかで争いごとに巻き込まれたばあい、戦わざるをえないことを自覚するのではないか。
著者によれば、子どもや子ども期の研究を戦争や軍事から切り離していて、その研究は始まったばかりだという。いっぽう日本ではその分野の研究は多くの研究蓄積があるという(山中恒の1連の著作など)。
この本は日本の子どもたちがどのように「戦争を遊んできたのか」、どのように日本の戦争と結びついてきたのか、そして国民国家の台頭と、戦争を行う中央集権化とともに「戦争ごっこ」が受け入れられたか。
日本が国家建設から帝国へと移行するにつれて、組織化され、地図を取り入れて、領土獲得を意識化していったか。子どもたちは、遊び場や本、雑誌、紙のゲームなどで同時代の地図作成、偵察、戦争、植民地化の実践をいかに真似たのかを、豊富な資料を参照して解き明かしている。
そして、子どもたちは、無垢で、政治的・道徳的に中立で純粋であるという思い込みがあるのだが、それは「感情資本」とよぶもので、軍隊や軍人に対しては子どもの脆弱性や無邪気さ、柔軟性が動員されてきた。これらは戦争への意志の文化的・政治的生産、及び再生生産のメカニズムであるという。
1945年の敗戦まで日本国民は、「国民皆兵」として兵役が義務化され、社会的にもその目的を育成するために戦争や軍隊へつながる宣伝や報道がなされた。小学生はやがて「少国民」と呼ばれて、学校において軍事訓練を受ける。しかし、アジア・太平洋戦争の敗北は、日本の軍国主義との決別をもたらし、大人と子どもは平和主義を抱きしめるように期待された。
50年代の子ども向け出版物で「戦記もの」が流行したが、そこでは直接に日本の軍国主義的な過去はあまり、とりあげられなかったという。60年代には『のらくろ』が復刊されてブームとなり、まんがでは『0戦はやと』が人気を博した。とはいえかつての戦争を肯定するような見方は主流にはなり得なかった。
今日での戦争ごっこは野原ではなく、コンピュータゲームであり、ネットの画面のなかであるという。これらの状況は「絶え間ない戦争」という物語を強固にしているという。それは国家自体の存立と、娯楽産業が関係してるからだろう。
本書の第四章では「戦争をクィアする」とのタイトルがつけられている。クィアするとは性的マイノリティについての用語らしいが、ここでは既存のカテゴリーに当てはまらないものとして扱われると考えてよさそうだ。
自衛隊はPRの戦略として「自己幼稚化」しているという。自衛隊の任務を子どもらしい、かわいらしいものの観点から表象する。その際に子ども向けの広告やポップカルチャーをモデルとした形式を用いることがそれである。
そして自衛隊が戦争/平和、男/女、子ども/サイボーグ、セックス/暴力の境界を越えたり、曖昧、再定義しているとして「戦争をクィア」していると語る。
これまでに「子ども性」や子ども使うのは、戦争を道徳的、自然化するためであった。可愛らしい子どもがいるだけで、破壊や暴力性が中和されてしまうが、無意識か意識的かどちらかにせよ、それは気づかなかった。それは今日の軍隊の存在自体や国民国家の境界を超えて存在するものである在日米軍についても当てはまる。
あからさまな軍人や軍事の称揚はできないが、戦争が起きている現実や防衛の必要性、武力よりも救助、救出活動の様子を見せたり、子どもとの結びつきを示すことにより自衛隊や日米同盟の戦争準備は、見えなくされている、私たちはそのことに気づくべきだろう。
(本田一美)

在日米軍が、日本の若者に日米同盟の意義を伝えようと作成したマンガ「わたしたちの同盟―永続的パートナーシップ」(2010年8月4日公開)。(c)AFP/US MILITARY(https://www.afpbb.com/articles/-/2745987 より)

「まりたん 英語のドリルF*CK編」この本は、アメリカ海兵隊で使われる「FUCK」用法を徹底解説、この一冊ですべて学習できると、(どこに需要があるのか不明だが)宣伝されている(アマゾンHPより)