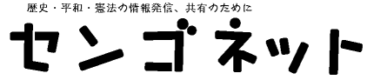プロパガンダとしての「戦争画」を越えて、継続する「非常時」の表象

会場風景。左から山口蓬春《香港島最後の総攻撃図》(1942)、藤田嗣治《哈爾哈河畔之戦闘》(1941)(tokyoartbeatより)

国立近代美術館と「コレクションを中心とした特集 記録をひらく 記憶をつむぐ」の案内。看板を見ても戦争を想起させるものではない
東京・竹橋の国立近代美術館で「コレクションを中心とした特集 記録をひらく 記憶をつむぐ」展が10月26日まで開催された。この展覧会には、いわゆる「戦争画」が24点を展示されていて、これまでで最大規模だという。終了する日になんとか間に合って、訪れることができた。
それにしても、東京国立近代美術館入り口に展覧会の掲示はされているが、その表示と絵の写真をみてもとても「戦争画」が展示されているとは思えない。なんとも地味な、よく分からないような表現となっている。なんでこうなっているのか。
東京新聞によると東京国立近代美術館は展覧会のちらしやポスターを作っていない。開催を知る方法は、同美術館のウェブサイトやメディアの記事に限られる。図録も作成されていない。理由は以下のとおりだ(東京新聞デジタル 2025年9月15日) 。
さらに不思議なのは展覧会のタイトル。「コレクションを中心とした特集 記録をひらく 記憶をつむぐ」と、戦争との関連性がわからない。会場のあいさつ文では「戦争体験を持たない世代がどのように過去に向き合うことができるかが問われている」と掲げるが、なぜ目立たない形で開催するのか。
(略)東京国立近代美術館側に意図を尋ねると、繰り返したのは「センセーショナルな宣伝をしたくなかった」との言葉だった。広報担当者は「美術館は歴史認識を問う立場ではなく、展示で戦争を扱うときはより丁寧な説明が必要。展示の文脈の意図と異なる切り取られ方をし、言葉が独り歩きすることは避けないといけない」と話す。

会場で展示に見入る人々。さほど宣伝もされいないが、多くの人がつめかけた

左は絵本『支那事変武勇談』1937年、右は『聖戦美術展集』1939年

雑誌「満州グラフ」のページ 1939年

大東亜共栄圏を示す地図
いろいろとたいへんなのである。さて、この展覧会、確かに戦争画だけを展示しているわけではない。戦争の時代に沿った絵画、そして当時の世相を伝えるハガキや出版物などのメディアが並んでいる。「たとえば『戦争画展』と銘打つことで、当館の保管する153点(の作戦記録画)すべてが一括公開されるような誤解は受けたくないという思いはありました。当館はこれまで一貫して、戦争記録画はあくまで歴史の流れのなかで位置づけを見ていくべきものという態度で公開を続けてきました」(ウェブサイト tokyoartbeat)
https://www.tokyoartbeat.com/articles/-/opening-documents-weaving-memories-momat-insight-202508

朝鮮・満州の旅行案内の冊子と朝鮮の風俗を紹介した絵葉書

「青少年義勇移民・満洲グラフ」1938年

「大東亜戦争と台湾青年:写真報道」1944年
この展覧会を説明するには私には手があまる、が誤解を恐れずにいえば「天皇のために死ぬことが良いとされた時代(戦前・戦中)から、主権在民の日本国憲法が成立した(象徴天皇制となった)民主主義といわれる戦後社会まで、いわば<昭和>の時代をとおして、戦争にかかわる表象をみる」ということになろうか。そのせいか個人的には絵画よりも、当時のビラや冊子、ポスター、写真などのメディアに目を見張った。たとえば植民地への旅行など…。当時は朝鮮、台湾、満州などの外地への旅は帝国主義の眼差しを伴いながら、大衆化されていった。絵葉書などで多くのひとの眼に触れて、やがて画家の主題ともなってくる。当然ながらそれには帝国主義政策の思惑があるのだが……。
戦争画という名称については、この展覧会では<境界が難しく、狭義には「戦争記録画」を使用していて、広義には総力戦を表象する絵画全体を指す>としている。
また戦争画についても、かつてのタブー視されていた状況から、正当に「美術作品」として評価しようじゃないか、という社会の変化もある。それについては、以下の視点はおさえておきたい。「たとえば藤田の《サイパン島同胞臣節を全うす》、サイパン島でアメリカ軍に攻められ、捕虜になるくらいならみずから命を絶とうとしている場面ですけれども、戦争中のこの絵を見た人たちは一種の殉教図として見たわけです。彼らを神々しいものと称える一方で、アメリカをいっそう憎む気持ちを燃え上がらせる。だから戦争中はプロパガンダとして役割を果たしていました。
それが戦後になると、まさにプロパガンダとしての性格が憎まれて悪者扱いされた。さらに戦争から遠く離れて二十一世紀になると、戦中の文脈の実感が薄れてしまい、単純に戦争の悲惨さだけ受け止めてしまって、これは反戦の絵ではないかという素朴な感想をもってしまう。あるいはもっと単純に、かっこいいというふうに見てしまう。(略)その意味では、絵は見る人自身の考えを映し出す鏡なんだとつくづく思います。」(大谷省吾「東京国立近代美術館の戦争記録画とその周辺」『いかに戦争は書かれたか』所収 BankART1929 2017年)
戦争「画」に限らず美術は多義的ではあるが、その「画」をとりまく時代・背景・文脈は理解・認識する必要があるだろう。

《シンガポール最後の日(ブキ・テマ高知)》 藤田嗣治 1942年 油彩・キャンバス

戦争記録画は宣伝効果を考えたか、大きなものが多い

「爆弾三勇士」(1932年)にまつわる印刷物など
要するに社会全体が戦時・戦争体制に呑み込まれていたのだ。社会がそのようなメディアにより包摂された「非常時」体制となった。その意味では絵画は制作するのに時間が一定かかるし、記念碑的なものにならざるを得ないのだろう。そして満洲国成立以降、より明確には「支那事変」以後の戦時により、ひとびとたちの日常は挙国一致の総力戦体制・皇国ナショナリズムへと統合が強化されていく。そのような状況を益田肇は「社会戦争」と呼んでいる。
益田氏は「戦争画」とはそもそも「社会戦争画」ではないかという。社会戦争とは聞き慣れない言葉だが、人びとの日常生活における争い、戦いを「社会戦争」だとしている。言葉をつなげれば共同体や社会、国家のあるべき姿をめぐる人びとの争いの数々だという。これを知るには、彼の著書(『人びとの社会戦争――日本はなぜ戦争への道を歩んだのか』岩波書店 2025年)を読むしかないのだが、ここでは、彼がこの展覧会評を描いた文章から引いた(益田肇『人びとが織りなす社会戦争』月刊「世界」2025年12月号 岩波書店)。それによれば、当時の画家たちは、国家の戦争を前提としているが、実は自らも含めて、多くの人が織りなす社会戦争を描いていたのではないかというものだ。
この展覧会の展示では入ってすぐに大日本帝國が現れて、帝国臣民への教育や日本を中心とした大東亜共栄圏が提示され、植民地への旅情をそそる。そしてその帝国を支えるための軍事行動や戦争体制が展示される。兵士たちや戦車、戦闘機の戦いだけではなく、銃後の人々の生活、国民生活にも影響はでてくる。主婦・女性、子供、植民地朝鮮の人々も動員される。さらに普通の人たちに空襲が襲いかかる。やがて原爆が投下され戦争は終わる。が、なおも展示は続く。これ以後は狭義の戦争画はなくなってくる。
これまでは勇ましい姿、あるいは「聖戦」を象徴する絵であったものが、戦後になるとあの戦争を問なおす、あるいは戦争の実相はなんだったのか、それを問いかける表現となってくる。そうして戦争や軍事のディテール、軍記ものや戦争のノスタルジックな「物語」が消費される時代となってくる。また、他国の戦争を表すものが出てくる。また戦争そのものの継続ではないかと思えるものも展示されている。展示も終了に近づいてくるが不安になってくる。まさに数カ月前に国会前で聞いた言葉が想起された。「戦争は終わっていない」ということ、あるいは「戦後はない。継続しているのだ」ということ。さらには「戦前という戦争準備」であり、反復をしているのだ、と。
(本田一美)

女性画家たちが集団制作した《大東亜戦皇国婦女皆働之図》(春夏の部)1944年

女性画家合作の《大東亜戦皇国婦女皆働之図》(秋冬の部)1944年

長崎や広島の原爆を扱った出版物。後ろには丸木位里・俊の「原爆の図」

《よみがえる亡霊》浜田知明 1956年 エッチング

東京大空襲の記録や水木しげるの戦記マンガなど

米軍基地の残る沖縄についての書籍など