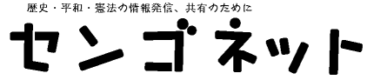東京大空襲から80年。追悼集会・資料展と浅草寺を巡る

天候に恵まれた追悼集会だった

参加者が次々に献花と祈りを捧げた。台東区の慰霊碑は1986年建立
3月10日(月)台東区・浅草の隅田公園内の東京大空襲犠牲者追悼碑前で大空襲の犠牲者を追悼する集会が開かれ、空襲を体験した方の証言が話された。主催は東京大空襲犠牲者追悼・記念資料展実行委員会。
都立横網町公園にある追悼碑は知っていたが、墨田公園のそれは知らなかった。言問橋に近い隅田公園台東区側の入り口北側にある追悼碑は、思ったよりも小さくささやかな印象を受けた。

台東区の碑の脇には戦災当時の言問橋の縁石が置かれている
■浅草寺の戦跡・史跡を巡る
追悼碑の前で冥福を祈り献花をして、台東区浅草公会堂ギャラリーでの東京大空襲資料展(3月7日~10日)へ向かう。その前に、資料展実行委員のガイドで浅草寺周辺の戦跡・史跡を巡るツアーに参加した。大空襲にまつわる様々な話が聞けた。
隅田公園から東参道・二天門通りを抜けて二天門をくぐり浅草寺境内へ入る。二天門の両脇にある像は戦時中には戦災を怖れて疎開させたそうだが、幸いなことに門そのものが消失を免れたということだ。
二天門を抜けると右側に浅草神社があるが、浅草寺は神仏習合だったところで、神社となるのは明治政府による神仏分離以降だ。神社は空襲の被害にあい、消失してしまった。空襲直後の写真を示して説明してくれた。

右が二天門、左が浅草神社

浅草神社の鳥居の前で、空襲で壊された当時の写真をかざして説明された
反対側には、弁天山の鐘楼があり、その鐘楼も被災して鐘だけが残った。また、浅草寺境内にはイチョウの木がたくさんあるが、イチョウは枝葉や幹に水分を沢山含んでいて、燃えにくく、それで植えられている。イチョウの木も被災して、焼け焦げたイチョウの木が残っている。被災したイチョウは10本ほどあるという。

焼夷弾を受けて黒焦げになったイチョウの木
境内には戦災慰霊の地蔵が複数ある。母子地蔵尊(まんしゅう母子地蔵)は旧満州移民が死別・不明となった母子の霊を慰めるとともに、残留婦人や残留孤児となって生き別れた母子の心の拠り所となるように、との願いが込められている。像のデザインは漫画家のちばてつや、碑文の文字は森田拳次だ。ともに満州引揚者でもある。1997年建立
すぐちかくにあるのは平和地蔵尊。東京大空襲で亡くなった人たちの霊を慰め、世界平和を祈念するものとして、龍郷定雄という篤志家の方が立てた。1949年建立

母子地蔵尊(まんしゅう母子地蔵)1997年建立

平和地蔵尊。1949年建立
そして、浅草寺の本堂に向かって左へとそれて行くと淡島堂がある。ここでは空襲の法要が終わったばかりで、丁度後片付けをしているところであった。ここは東京大空襲で本堂が焼失した後、一時期仮本堂となった。
この小さな敷地には、大平和塔と戦災供養地蔵尊がある。大平和塔は、浅草地区の3万人余の戦災殉難者の霊をまつる。現代的な意匠であり、台座の銘には湯川秀樹博士の直筆「みたまよ、とこしえに、安らかに、われら守らん、世界の和」と刻まれている。1963年建立
手前には戦災供養地蔵(戦災霊供養 地蔵大菩薩)があり、戦災で亡くなった浅草の花柳街の人々の霊を慰めるため旧浅草藝妓屋組合が建立したものだ。1962年建立

中央に和の文字が見える浅草大平和塔。1963年建立

戦災供養地蔵。1962年建立

今の浅草公会堂と空襲当時の惨状を写真で比較した
■東京大空襲資料展
浅草公会堂の一階では東京大空襲資料展が開催されていた。ガイドの方が、この場所で、当時の焼け野原となっている写真を見せてくれた。浅草公会堂自体は戦後のものだが、戦時中は役所として機能していたのだ。
浅草公会堂のギャラリーはやや狭いが、それでも史料、当時の地図や写真、雑誌・文書類、焼夷弾の説明、戦中の日常生活用品、もんぺ姿やスフの国民服、防空頭の衣服などが展示されていた。被災体験者たちの絵画、体験者のインタビュー映像など充実した展示だった。
東京大空襲は「昭和20(1945)年3月10日未明、現在の台東・墨田・江東区のいわゆる下町地区は、米軍の爆撃機B29による空襲を受け、死者およそ10万人、負傷者4万人、罹災者100万人という未曾有(みぞう)の大被害を被った。東京大空襲と呼ばれるこの空襲は、夜間に住宅の密集地を目標にして、約1700トンもの焼夷弾を投下し、根こそぎ焼き尽くすというものであった。」(総務省HP)
1日の死者数だけでも広島・長崎に匹敵する被害を受けながら、東京大空襲についての扱いは軽んじられている。その理由については以前にも書いたが、再説しよう。敗戦直後にGHQは、東京大空襲の犠牲者慰霊搭の建立について禁止する指令を出している、それが独立国となっても意識のうえで継続している。いわば思考停止状態なのだ。残念ながら日本はいまだに米国の従属国であり、奴隷根性が残っていると言わざるをえない。つまり日本の支配層の米国への忖度であり、また、かつての戦争の責任、支配責任の隠蔽でもあるだろう。
歴代の政府や東京都が見せたくないもの、伝えたくないものとして扱われてきた「東京大空襲の記憶」。市民の手によって戦争の惨禍、受難の記憶と記録は継承されてはいるが、十分とは言えない。慰霊碑や地蔵などは見てきたように、現在でも複数あって、個人が建立したものなど、それはそれで、貴重なのだが、なにより、多くの人たち共有するために、メモリアルとして歴史を刻むための場と空間が求められるだろう。公共的な空間のなかで想いを想起する、心をつなぐ、皆に知られる場所をつくろうではないか。
(本田一美)

平和塔のすぐ隣には被害を示すプレートがあった

釣鐘だけが石垣の上に残っていた(当時の写真)

浅草公会堂のギャラリーでの東京大空襲資料展

空襲に備えた当時の服装を展示

展示物。右下は御札だが、まさに神仏だのみをするしかないのだった

右は焼夷弾。左に灯火管制指導要領

左上は灯火管制のため電球につけるカバー

防火演習を伝える写真

戦時中の日用品などの展示物。興味深く見ている方が多い

戦時中の雑誌や教科書など貴重なものが展示されていた

大空襲米国爆撃機の飛行経路

敗戦後に紙くずとなった戦時国債

本所区民の罹災証明書

当時の写真。出征軍人の走行会

当時の写真。防火演習と実際の消火活動

大空襲体験者の絵

当時の写真。消失した浅草地下鉄入口

当時の写真。浅草仲見世も周囲が何も無い

台東区内の慰霊碑など史跡一覧を紹介・展示していた

東京大空襲資料展チラシ